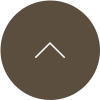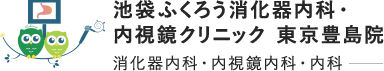痔の痛みや違和感に悩む方が知っておくべき診療内容



院長 柏木 宏幸所属学会・資格
- 日本内科学会 総合内科専門医
- 日本内科学会 内科認定医
- 日本消化器病学会 消化器病専門医
- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
- 一般社団法人日本病院総合診療医学会
認定病院総合診療医 - 難病指定医
- がん診療に関わる医師に対する緩和ケア 研修会 修了
- PEG・在宅医療研究会 修了証
痔とは?その種類と特徴
 痔(じ)は、日本人の3人に1人が経験するといわれるほど一般的な疾患です。肛門周辺の血管や皮膚に異常が生じることで発症し、日常生活に支障をきたすこともあります。痔は誰にでも起こり得る病気ですが、種類によって症状や治療法が異なります。正しく理解することで、適切な対処ができるようになります。
痔(じ)は、日本人の3人に1人が経験するといわれるほど一般的な疾患です。肛門周辺の血管や皮膚に異常が生じることで発症し、日常生活に支障をきたすこともあります。痔は誰にでも起こり得る病気ですが、種類によって症状や治療法が異なります。正しく理解することで、適切な対処ができるようになります。
痔の主な種類
①いぼ痔(痔核)
 肛門周辺の血管がうっ血し、こぶのように腫れる状態をいぼ痔(痔核)といいます。いぼ痔には「内痔核」と「外痔核」の2種類があります。
肛門周辺の血管がうっ血し、こぶのように腫れる状態をいぼ痔(痔核)といいます。いぼ痔には「内痔核」と「外痔核」の2種類があります。
内痔核
肛門の内側にできるいぼ痔で、初期のうちは痛みを感じにくいですが、進行すると出血や違和感が現れます。悪化すると、肛門の外に飛び出す(脱出する)ことがあり、指で押し戻さなければ戻らなくなることもあります。
外痔核
肛門の外側にできるいぼ痔で、腫れや痛みが強く、特に座ると違和感を覚えることが多いです。内痔核とは異なり、出血は少なめですが、日常生活での不快感が大きくなります。
②切れ痔(裂肛)
便秘などで硬い便が出る際に肛門が切れてしまう状態を切れ痔(裂肛)といいます。排便時に鋭い痛みを感じるのが特徴で、出血を伴うことが多いです。傷口が慢性化すると、肛門が狭くなってしまい、排便がさらに困難になることもあります。
③痔ろう
細菌感染が原因で、肛門周囲に膿がたまり、トンネルのような管(瘻管)ができる状態を痔ろうといいます。初期段階では腫れや違和感が主な症状ですが、進行すると膿が排出され、悪臭を伴うことがあります。放置すると瘻管が複雑化し、手術が必要になることがほとんどです。
痔の主な原因とは?
痔の原因は、生活習慣や環境、体質によるものなどさまざまです。特に、以下のような要因が重なることで発症しやすくなります。
排便のトラブル
 最も多い原因の一つが便秘や下痢です。便秘になると硬い便を無理に出そうといきむため、肛門が傷つきやすくなります。その結果、切れ痔やいぼ痔が発生しやすくなります。反対に、下痢が続くと肛門に刺激を与え、炎症が起こることもあります。
最も多い原因の一つが便秘や下痢です。便秘になると硬い便を無理に出そうといきむため、肛門が傷つきやすくなります。その結果、切れ痔やいぼ痔が発生しやすくなります。反対に、下痢が続くと肛門に刺激を与え、炎症が起こることもあります。
長時間の座り仕事・立ち仕事
 デスクワークや運転業務など、長時間座ったままでいると肛門周辺の血流が悪くなり、うっ血しやすくなります。逆に、立ち仕事も血流の滞りを招くため、痔のリスクを高める原因となります。適度に休憩をとり、ストレッチを取り入れることが予防につながります。
デスクワークや運転業務など、長時間座ったままでいると肛門周辺の血流が悪くなり、うっ血しやすくなります。逆に、立ち仕事も血流の滞りを招くため、痔のリスクを高める原因となります。適度に休憩をとり、ストレッチを取り入れることが予防につながります。
妊娠・出産
妊娠中はホルモンバランスの変化や子宮の圧迫によって血流が悪化し、いぼ痔ができやすくなります。また、出産時の強いいきみが肛門への負担となり、出産後に痔を発症する女性も多いです。
食生活の乱れ
 食物繊維の不足や、水分摂取量の減少は便秘を引き起こす原因になります。アルコールや香辛料の過剰摂取は肛門を刺激し、炎症を引き起こす可能性があります。バランスの取れた食生活が痔の予防につながります。
食物繊維の不足や、水分摂取量の減少は便秘を引き起こす原因になります。アルコールや香辛料の過剰摂取は肛門を刺激し、炎症を引き起こす可能性があります。バランスの取れた食生活が痔の予防につながります。
ストレスと運動不足
 ストレスが溜まると自律神経のバランスが崩れ、腸の働きが低下して便秘になりやすくなります。また、運動不足は血流を悪化させ、痔の発症リスクを高めます。適度な運動やリラックスする時間を作ることが、痔の予防にも効果的です。
ストレスが溜まると自律神経のバランスが崩れ、腸の働きが低下して便秘になりやすくなります。また、運動不足は血流を悪化させ、痔の発症リスクを高めます。適度な運動やリラックスする時間を作ることが、痔の予防にも効果的です。
痔の主な症状と違和感の種類
 痔の症状は種類によって異なりますが、共通して見られるのが排便時の痛み、出血、違和感です。初期のうちは気づきにくいこともありますが、放置すると悪化し、日常生活に支障をきたすこともあります。
痔の症状は種類によって異なりますが、共通して見られるのが排便時の痛み、出血、違和感です。初期のうちは気づきにくいこともありますが、放置すると悪化し、日常生活に支障をきたすこともあります。
いぼ痔(内痔核・外痔核)の症状
内痔核は初期のうちは痛みを感じにくく、排便時に鮮血が便やトイレットペーパーにつく程度です。しかし、進行すると腫れが大きくなり、肛門の外に飛び出すことがあります。軽度であれば自然に戻りますが、重症化すると指で押し戻さないと戻らなくなり、最終的には手術が必要になることもあります。外痔核は肛門の外側に発生するため、腫れや痛みを伴うことが多いです。特に座ったり歩いたりすると強い違和感があり、悪化すると血栓(血の塊)ができ、激しい痛みを引き起こすこともあります。
切れ痔(裂肛)の症状
切れ痔の主な症状は排便時の鋭い痛みと出血です。傷口が治りきらないうちに排便を繰り返すと、傷が深くなり慢性化することがあります。慢性化すると肛門が狭くなり、より強い痛みを感じるようになるため、早めの治療が重要です。
痔ろうの症状
痔ろうは初期段階では肛門周囲に腫れや違和感を感じる程度ですが、進行すると膿がたまり、排出されるようになります。膿が出る際に痛みを伴うこともあり、放置すると発熱や悪臭の原因にもなります。自然治癒することはなく、手術が必要となるケースがほとんどです。
自己判断できる?痔のセルフチェック方法
痔の症状があると感じた場合、まずはセルフチェックを行うことで、自分の状態を把握できます。セルフチェックをする際には、排便時の違和感や出血の有無、腫れの状態などに注目することが大切です。もちろん、自己判断で危険ではないと判断することは危険ですので、あくまで一つの基準として考えて下さい。
排便時の痛みの有無
 痔の初期段階では、痛みをほとんど感じないこともありますが、進行すると排便時の痛みが強くなります。特に切れ痔(裂肛)の場合は、便が通るたびに鋭い痛みを感じるのが特徴です。いぼ痔の場合、内痔核の初期では痛みが少ないですが、外痔核や進行した内痔核では激しい痛みを伴うことがあります。
痔の初期段階では、痛みをほとんど感じないこともありますが、進行すると排便時の痛みが強くなります。特に切れ痔(裂肛)の場合は、便が通るたびに鋭い痛みを感じるのが特徴です。いぼ痔の場合、内痔核の初期では痛みが少ないですが、外痔核や進行した内痔核では激しい痛みを伴うことがあります。
出血の有無
 トイレットペーパーに鮮血がついたり、便器の水が赤く染まったりする場合は、内痔核や切れ痔の可能性が高いです。ただし、黒っぽい血が混ざっている場合や便全体が赤く染まっている場合は、痔ではなく大腸の病気が原因であることもあるため、専門医への相談が必要です。
トイレットペーパーに鮮血がついたり、便器の水が赤く染まったりする場合は、内痔核や切れ痔の可能性が高いです。ただし、黒っぽい血が混ざっている場合や便全体が赤く染まっている場合は、痔ではなく大腸の病気が原因であることもあるため、専門医への相談が必要です。
肛門周囲の腫れや違和感
肛門の外側にしこりや腫れを感じる場合、外痔核の可能性があります。内痔核の場合、腫れが進行すると肛門の外に脱出し、指で押し戻さなければ戻らなくなることもあります。
膿や異臭の有無
肛門周囲から膿が出る、または強い悪臭がする場合は、痔ろうの可能性が高いです。痔ろうは自然に治ることはなく、放置すると症状が悪化するため、早めに医療機関を受診することが大切です。
痔の診療を受けるべきタイミング
 痔の症状が出たとき、どのタイミングで病院を受診すればよいのか迷う人は多いです。軽い違和感や出血があるものの、痛みがない場合は様子を見てしまうことが一般的ですが、放置することで症状が進行し、治療が長引くケースも少なくありません。痔は初期の段階で適切なケアを行うことで、悪化を防ぐことができます。そのため、自己判断で放置せず、診療を受けるべきタイミングを見極めることが大切です。
痔の症状が出たとき、どのタイミングで病院を受診すればよいのか迷う人は多いです。軽い違和感や出血があるものの、痛みがない場合は様子を見てしまうことが一般的ですが、放置することで症状が進行し、治療が長引くケースも少なくありません。痔は初期の段階で適切なケアを行うことで、悪化を防ぐことができます。そのため、自己判断で放置せず、診療を受けるべきタイミングを見極めることが大切です。
排便時に血が出る場合
排便時に血が出る場合は、痔の初期症状の可能性があります。特に、便に鮮血が付着している場合や、トイレットペーパーに血がつく程度の出血は、内痔核や切れ痔が原因であることが多いです。ただし、黒っぽい便や血が混じっている場合は、痔ではなく大腸の病気が関係している可能性もあるため注意が必要です。出血が続く場合や、出血量が多い場合は、速やかに医療機関を受診することが望ましいです。
肛門周辺に強い痛みや違和感がある場合
肛門周辺に強い痛みや違和感がある場合も、受診を考えるべきタイミングの一つです。特に、座るだけで痛みを感じる場合や、腫れが大きくなっている場合は、外痔核や血栓性外痔核(血の塊ができる痔)の可能性があります。外痔核は痛みが強くなると日常生活に支障をきたすため、早めの診察が必要です。
痔ろうが疑われる症状が出た場合
痔ろうが疑われる症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診するべきです。肛門周囲に膿がたまって腫れたり、膿が出ることで悪臭を感じたりする場合、放置すると感染が広がり、発熱を伴うこともあります。痔ろうは自然に治ることがなく、手術が必要になることが多いため、早期の治療が重要です。
このように、痔の症状は放置すると悪化することが多いため、少しでも異常を感じたら早めに医師の診察を受けることが大切です。初期の段階で適切な治療を受けることで、手術を回避できるケースもあるため、自己判断で放置しないことが望ましいです。
どの診療科を受診すべきか?
 痔の診療を受けると決めたとき、どの診療科を受診すればよいのか迷うことがあるかもしれません。痔の専門診療を行っているのは肛門科ですが、病院によっては消化器内科や外科でも診察を受けることができます。自分の症状に適した診療科を選ぶことで、スムーズに治療を受けることが可能になります。
痔の診療を受けると決めたとき、どの診療科を受診すればよいのか迷うことがあるかもしれません。痔の専門診療を行っているのは肛門科ですが、病院によっては消化器内科や外科でも診察を受けることができます。自分の症状に適した診療科を選ぶことで、スムーズに治療を受けることが可能になります。
肛門科は、痔の診療を専門とする科であり、最も適切な診療を受けることができる場所です。肛門科のある病院では、専門の医師が診察を行い、症状に応じた治療を提案してくれます。軽度の症状であれば、薬や生活習慣の指導によって改善が見込めるため、早めの受診が有効です。
消化器内科や消化器外科でも、痔の診療を行うことがあります。特に、出血が続く場合や、腸の異常が疑われる場合には、消化器の専門医が診察を行うことが望ましいです。痔と同時に、大腸の疾患や腸の炎症などが隠れている可能性もあるため、詳しい検査を受けることが必要になることもあります。当院では、しっかりと消化器内科専門医が診察、検査、治療を行います。
女性の場合、診察時の恥ずかしさが気になることもありますが、最近では女性医師が診察を行う病院も増えてきています。事前に病院の情報を調べ、女性医師がいる病院を選ぶことで、安心して診察を受けることができます。
痔の診療の流れと検査内容
 病院を受診する際、どのような流れで診療が進むのかを知っておくことで、不安を軽減することができます。診察は、問診、視診(肛門鏡)・触診、必要に応じて内視鏡検査(大腸カメラ)という流れで進められます。
病院を受診する際、どのような流れで診療が進むのかを知っておくことで、不安を軽減することができます。診察は、問診、視診(肛門鏡)・触診、必要に応じて内視鏡検査(大腸カメラ)という流れで進められます。
痔の診療の流れ
①問診
最初に行われるのが問診です。医師は、症状がいつからあるのか、出血の有無や頻度、痛みの程度、便秘や下痢の傾向などを聞き取ります。症状について正確に伝えることで、適切な診断につながります。
②視診や触診
肛門の状態を直接確認する視診や触診が行われます。医師は肛門周囲の腫れや赤み、しこりの有無をチェックし、必要に応じて指診を行います。指診では、指を肛門に入れて内部の状態を確認し、肛門鏡を用いて痔の程度やほかの異常がないかを調べます。診察はできるだけ痛みを感じないように行われるため、過度に心配する必要はありません。
③肛門鏡検査や大腸内視鏡検査
出血が続いている場合や、大腸の異常が疑われる場合は、肛門鏡や大腸内視鏡(大腸カメラ)を用いた検査を行うことがあります。これは、痔以外の病気がないかを確認するために重要な検査です。特に、出血が長期間続いている場合は、大腸ポリープや大腸がんなどの可能性を排除するために行われます。
恥ずかしくない?痔の受診時の不安と対策
 痔の診察を受ける際、多くの人が「恥ずかしい」「抵抗がある」と感じるかもしれません。特に、肛門の診察を受けることに対して心理的なハードルを感じる人は少なくありません。しかし、痔は決して珍しい病気ではなく、医師にとっては日常的に診察する疾患の一つです。そのため、過度に恥ずかしがる必要はなく、適切な診療を受けることで早期回復につながります。当院におきましても、毎日痔で悩まれる多くの患者さんが来院されております。
痔の診察を受ける際、多くの人が「恥ずかしい」「抵抗がある」と感じるかもしれません。特に、肛門の診察を受けることに対して心理的なハードルを感じる人は少なくありません。しかし、痔は決して珍しい病気ではなく、医師にとっては日常的に診察する疾患の一つです。そのため、過度に恥ずかしがる必要はなく、適切な診療を受けることで早期回復につながります。当院におきましても、毎日痔で悩まれる多くの患者さんが来院されております。
受診時の不安を軽減するために
受診時の不安を軽減するためには、まず医療機関の選び方を工夫することが重要です。女性の場合、女性医師が診察を行うクリニックを選ぶことで、精神的な負担を減らすことができます。また、痔の専門クリニックでは、診察の際に患者のプライバシーを考慮した対応がなされることが多く、患者さんの負担を最小限に抑える工夫がされています。診察の際、服を全部脱がなければならないのではないかと不安に思う人もいるかもしれませんが、実際には必要最小限の範囲だけ(おしりだけ)露出する形で診察が行われます。多くの医療機関では、タオルをかけたりすることで、患者が恥ずかしさを感じにくいよう配慮されています。
患者様の負担を減らすために
診察の際に強い痛みを感じるのではないかと心配する人もいます。実際には、医師はできるだけ患者の負担を減らすように配慮しながら診察を行うため、痛みを最小限に抑えた検査が実施されます。緊張すると肛門の筋肉がこわばり、痛みを感じやすくなるため、できるだけリラックスすることが大切です。診察が終わった後は、医師から診断結果と治療方法について説明を受けることになります。症状の程度によっては、生活習慣の改善や薬の処方だけで治療が可能な場合もあります。手術が必要なケースでも、最近では負担の少ない治療法が増えているため、過度に心配する必要はありません。
受診をためらうことで、症状が進行し、より治療が難しくなるケースもあります。恥ずかしさを感じる気持ちは自然なものですが、健康を優先し、早めに専門医の診察を受けることが最善の選択です。
痔の治療方法の種類とそれぞれの特徴
 痔の治療方法は、症状の程度によって異なります。軽症の場合は生活習慣の改善や薬の使用で対処できますが、進行した場合には手術が必要になることもあります。それぞれの治療方法の特徴を理解し、自分に合った治療を受けることが大切です。
痔の治療方法は、症状の程度によって異なります。軽症の場合は生活習慣の改善や薬の使用で対処できますが、進行した場合には手術が必要になることもあります。それぞれの治療方法の特徴を理解し、自分に合った治療を受けることが大切です。
軽度の痔の場合
軽度の痔の場合、まず行われるのが薬物療法です。市販の軟膏や坐薬、飲み薬などを使用し、炎症や腫れを抑えることで症状の改善を目指します。塗り薬や坐薬は、直接患部に作用するため、痛みやかゆみ、出血を素早く和らげることができます。飲み薬は血流を改善し、痔の悪化を防ぐ効果があります。薬を使用するだけでなく、食生活を改善し、排便習慣を整えることも重要です。症状が進行し、薬だけでは改善が見込めない場合は、硬化療法やゴム輪結紮術などの処置が行われることがあります。硬化療法は、痔核に薬剤を注入し、血流を遮断することで痔を縮小させる治療法です。ゴム輪結紮術は、内痔核の根元をゴムで縛り、血流を遮断して自然に脱落させる方法です。これらの治療は比較的負担が少なく、日帰りで受けることができる場合もあります。
重症化した痔の場合
重症化した痔の場合、手術が必要になることもあります。手術には、痔核を切除する「痔核切除術」や、血流を遮断して痔を縮小させる「PPH法(吻合器痔核手術)」などがあります。最近では、痛みや出血が少ないレーザー治療や、術後の回復が早い治療法も増えており、以前に比べて手術の負担は軽減されています。治療法を選択する際には、症状の程度だけでなく、生活スタイルや希望に応じた方法を医師と相談しながら決めることが大切です。軽症のうちに適切な治療を受けることで、手術を回避できる場合もあるため、早めの対応が重要です。
当院では実施できる治療とできない治療があります。さらに手術など高度な治療が必要な場合は、適切な医療機関へご紹介いたします。
ご予約はこちらから
当院では、痔でお悩みの方に丁寧に診察と検査を行います。場合によっては、肛門鏡検査や内視鏡検査のご提案もいたします。まずは、外来のご予約のうえご来院ください。24時間web予約が可能です。