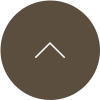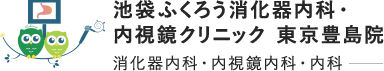胃痛や吐き気が同時に起こる場合に考えられる疾患とは



院長 柏木 宏幸所属学会・資格
- 日本内科学会 総合内科専門医
- 日本内科学会 内科認定医
- 日本消化器病学会 消化器病専門医
- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
- 一般社団法人日本病院総合診療医学会
認定病院総合診療医 - 難病指定医
- がん診療に関わる医師に対する緩和ケア 研修会 修了
- PEG・在宅医療研究会 修了証
- 胃痛と吐き気が同時に起きているとき、体の中では何が起きているのか?
- 急性胃炎:ストレスや食生活の乱れが原因で起こる胃の炎症
- 慢性胃炎:ピロリ菌感染による胃のダメージとは?
- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍:胃酸が粘膜を傷つける病気
- 逆流性食道炎:胃酸の逆流がもたらす痛みと不快感
- 機能性ディスペプシア:検査では異常なし?ストレス性胃痛の正体
- 胃がん:初期症状としての胃痛と吐き気に注意
- 胆石症や胆のう炎:胃痛と吐き気が胆のうの病気によることも
- 膵炎:みぞおちの痛みと吐き気が続く場合に疑うべき疾患
- 腸閉塞(イレウス):胃痛と吐き気に加えてお腹が張る症状に注意
- 食中毒や感染性胃腸炎:突然の激しい症状の正体とは?
- 心筋梗塞:胃痛と吐き気が隠れた心疾患のサインであることも
- ご予約はこちらから
胃痛と吐き気は、日常的に起こることのある症状ですが、これらが同時に発生する場合、単なる胃の不調ではなく、さまざまな病気が関係している可能性があります。特に、食べ過ぎや飲みすぎ、ストレスによる一時的なものだけでなく、胃や腸の病気、胆のうや膵臓の疾患、さらには心疾患が関係していることもあるため、軽視せずに適切な対処をすることが重要です。本記事では、胃痛と吐き気が同時に起こる際に考えられる疾患を詳しく解説し、それぞれの特徴や注意すべき症状について紹介します。症状の原因を知ることで、適切な対応をとり、必要に応じて医療機関を受診する判断の参考にしてください。
胃痛と吐き気が同時に起きているとき、体の中では何が起きているのか?
 胃痛と吐き気が同時に発生しているとき、体内ではどのような変化が起こっているのでしょうか?これらの症状が起こる背景には、胃や腸だけでなく、自律神経やホルモンバランス、他の臓器の影響が関わっていることがあります。
胃痛と吐き気が同時に発生しているとき、体内ではどのような変化が起こっているのでしょうか?これらの症状が起こる背景には、胃や腸だけでなく、自律神経やホルモンバランス、他の臓器の影響が関わっていることがあります。
①胃の粘膜が刺激され、炎症が起きている
 胃の粘膜は、胃酸や食べ物の影響を受けながらも、「粘液」を分泌することで自らを守っています。しかし、ストレスや刺激物の摂取、感染などの要因でこのバランスが崩れると、胃酸が直接粘膜を傷つけ、炎症を引き起こします。この状態が急性胃炎や胃潰瘍の原因となり、胃痛や吐き気が同時に現れることがあります。
胃の粘膜は、胃酸や食べ物の影響を受けながらも、「粘液」を分泌することで自らを守っています。しかし、ストレスや刺激物の摂取、感染などの要因でこのバランスが崩れると、胃酸が直接粘膜を傷つけ、炎症を引き起こします。この状態が急性胃炎や胃潰瘍の原因となり、胃痛や吐き気が同時に現れることがあります。
②自律神経の乱れが胃の働きを低下させている
 胃の動きは、自律神経によってコントロールされています。交感神経が優位になると、胃の動きが抑制され、消化が滞ることで不快感や胃の膨満感を引き起こします。特に、強いストレスを感じると、胃のぜん動運動が低下し、消化不良による胃痛や吐き気を招くことがあります。
胃の動きは、自律神経によってコントロールされています。交感神経が優位になると、胃の動きが抑制され、消化が滞ることで不快感や胃の膨満感を引き起こします。特に、強いストレスを感じると、胃のぜん動運動が低下し、消化不良による胃痛や吐き気を招くことがあります。
③消化管ホルモンの異常が起きている
 胃や腸は、消化管ホルモンによって消化機能を調整しています。しかし、食生活の乱れやストレスなどが影響すると、胃酸分泌を抑えるホルモン(セクレチンなど)の分泌が低下し、胃酸過多による胃痛が発生することがあります。また、消化管ホルモンのバランスが乱れると、胃の動きが鈍くなり、食べ物が長時間胃に留まることで吐き気が引き起こされることもあります。
胃や腸は、消化管ホルモンによって消化機能を調整しています。しかし、食生活の乱れやストレスなどが影響すると、胃酸分泌を抑えるホルモン(セクレチンなど)の分泌が低下し、胃酸過多による胃痛が発生することがあります。また、消化管ホルモンのバランスが乱れると、胃の動きが鈍くなり、食べ物が長時間胃に留まることで吐き気が引き起こされることもあります。
④他の臓器の異常が影響を及ぼしている
 胃の痛みと吐き気は、胃そのものの異常だけでなく、胆のうや膵臓、心臓などの異常によって引き起こされることもあります。例えば、胆石症や胆のう炎では胆汁の流れが悪くなり、脂肪の消化が困難になり胃痛や吐き気を引き起こします。さらに、心筋梗塞などの心疾患でも、胃痛や吐き気に似た症状が現れることがあるため、慎重な判断が必要です。
胃の痛みと吐き気は、胃そのものの異常だけでなく、胆のうや膵臓、心臓などの異常によって引き起こされることもあります。例えば、胆石症や胆のう炎では胆汁の流れが悪くなり、脂肪の消化が困難になり胃痛や吐き気を引き起こします。さらに、心筋梗塞などの心疾患でも、胃痛や吐き気に似た症状が現れることがあるため、慎重な判断が必要です。
このように、胃痛と吐き気が同時に起きている場合、単に「胃の調子が悪い」と考えるのではなく、体全体のバランスが崩れている可能性も視野に入れることが重要です。可能性のある疾患について説明していきます。
急性胃炎:ストレスや食生活の乱れが原因で起こる胃の炎症
急性胃炎は、胃の粘膜が急激に炎症を起こす病気で、胃痛と吐き気が同時に現れる代表的な疾患のひとつです。主な原因としては、ストレス、暴飲暴食、刺激の強い食べ物の摂取、過度なアルコール摂取、細菌やウイルス感染、薬の副作用などが挙げられます。特に、仕事や家庭のストレスが続くと、自律神経のバランスが崩れ、胃酸の分泌が過剰になりやすくなります。その結果、胃の粘膜が傷つきやすくなり、胃痛や吐き気を引き起こします。また、暴飲暴食や香辛料の多い食事は、胃の粘膜を刺激し、炎症を悪化させる要因となります。
症状の特徴
急性胃炎では、みぞおち周辺に痛みを感じることが多く、キリキリとした痛みが突然現れるのが特徴です。また、吐き気や嘔吐を伴うこともあり、場合によっては胃のむかつきや食欲不振を感じることもあります。特に、食後に症状が悪化することが多く、胃の張りや不快感を強く感じることがあります。
治療と対策
急性胃炎の治療では、まず胃を休めることが最優先です。症状がひどい場合は、数時間から半日程度の絶食を行い、水分補給を意識しながら胃に負担をかけないようにします。食事を再開する際は、消化の良いものを選び、刺激の強い食べ物やアルコールは避けることが重要です。また、胃酸の分泌を抑えるために、H2ブロッカーやプロトンポンプ阻害薬(PPI)、ボノプラザン(PCab)といった胃薬が処方されることが多いです。これらの薬は胃酸を抑えることで胃の粘膜を保護し、炎症を和らげる働きがあります。
急性胃炎は適切な対処をすれば数日で回復することが多いですが、黒い便(タール便)や吐血がある場合は、胃の粘膜が深く傷ついている可能性があるため、速やかに医療機関を受診することが必要です。
慢性胃炎:ピロリ菌感染による胃のダメージとは?
慢性胃炎は、胃の粘膜に長期間にわたって炎症が続く状態を指します。特に、日本人に多いピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)の感染が大きく関与していることが知られています。ピロリ菌は胃の粘膜に定着し、炎症を引き起こすことで、胃の防御機能を低下させてしまいます。その結果、胃痛や吐き気といった症状が慢性的に続くことがあります。
ピロリ菌が引き起こす影響
 ピロリ菌に感染すると、胃の粘膜が徐々に損傷を受け、胃酸の刺激に弱くなるため、胃痛や不快感が起こりやすくなります。また、長期間放置すると、胃潰瘍や胃がんのリスクが高まることが知られています。ピロリ菌感染があるかどうかは、血液検査、尿素呼気試験、便検査、胃カメラ検査などで確認することができます。
ピロリ菌に感染すると、胃の粘膜が徐々に損傷を受け、胃酸の刺激に弱くなるため、胃痛や不快感が起こりやすくなります。また、長期間放置すると、胃潰瘍や胃がんのリスクが高まることが知られています。ピロリ菌感染があるかどうかは、血液検査、尿素呼気試験、便検査、胃カメラ検査などで確認することができます。
症状の特徴
慢性胃炎の症状は、急性胃炎とは異なり、比較的軽い胃の不快感が長期間続くのが特徴です。食後の胃もたれ、みぞおちの痛み、胃の張り、吐き気、食欲不振などがよく見られます。特に、食事の後に胃が重く感じる場合は、慢性胃炎の可能性が高いです。
治療と対策
ピロリ菌が原因の慢性胃炎の場合、除菌治療(抗生物質と胃薬の併用)を行うことで、胃の炎症を改善できる可能性があります。除菌治療を成功させることで、胃の粘膜のダメージを軽減し、胃がんのリスクを下げることができます。
また、胃に優しい食生活を心がけることも重要です。消化の良い食事を心がけ、アルコールやカフェイン、香辛料などの刺激物を避けることで、胃の負担を軽減することができます。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍:胃酸が粘膜を傷つける病気
 胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、胃酸の影響で胃や十二指腸の粘膜が損傷し、深い傷(潰瘍)ができる病気です。主な原因は、ピロリ菌感染、過度なストレス、長期間の痛み止め(NSAIDs)の使用などが挙げられます。胃酸が過剰に分泌されることで、粘膜が傷つきやすくなり、胃痛や吐き気を引き起こします。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、胃酸の影響で胃や十二指腸の粘膜が損傷し、深い傷(潰瘍)ができる病気です。主な原因は、ピロリ菌感染、過度なストレス、長期間の痛み止め(NSAIDs)の使用などが挙げられます。胃酸が過剰に分泌されることで、粘膜が傷つきやすくなり、胃痛や吐き気を引き起こします。
症状の特徴
胃潰瘍では、食後にみぞおちの痛みが強くなることが多く、逆に十二指腸潰瘍では、空腹時に痛みが出るのが特徴です。その他、胃の不快感、吐き気、胸焼け、胃もたれ、黒いタール便(出血がある場合)が見られます。
治療と対策
胃潰瘍や十二指腸潰瘍の治療には、胃酸の分泌を抑えるH2ブロッカー、PPI(プロトンポンプ阻害薬)、ボノプラザン(PCab)のいずれかが使用されます。ピロリ菌感染が原因の場合は、除菌治療を行うことで、再発リスクを下げることが可能です。
食事面では、胃に優しい食べ物を選び、脂っこいもの、辛いもの、アルコールなど、胃を刺激する食べ物は避けることが大切です。また、ストレスが潰瘍を悪化させることがあるため、適度な休息やリラックスする習慣を取り入れることも有効です。
逆流性食道炎:胃酸の逆流がもたらす痛みと不快感
 逆流性食道炎は、胃酸が食道へ逆流することで、食道の粘膜が炎症を起こす病気です。胃と食道の間には「下部食道括約筋」という筋肉があり、通常は胃酸が逆流しないように働いています。しかし、この筋肉が緩んだり、胃の圧力が高まったりすると、胃酸が食道へ逆流し、食道粘膜を傷つけてしまいます。
逆流性食道炎は、胃酸が食道へ逆流することで、食道の粘膜が炎症を起こす病気です。胃と食道の間には「下部食道括約筋」という筋肉があり、通常は胃酸が逆流しないように働いています。しかし、この筋肉が緩んだり、胃の圧力が高まったりすると、胃酸が食道へ逆流し、食道粘膜を傷つけてしまいます。
主な原因
逆流性食道炎は、食生活の乱れや生活習慣の影響が大きい病気です。高脂肪食の摂取、食べ過ぎ、寝る前の飲食、肥満、ストレス、アルコールやカフェインの過剰摂取などが発症のリスクを高めます。また、加齢によって食道括約筋の機能が低下すると、逆流しやすくなることもあります。
症状の特徴
逆流性食道炎の治療では、胃酸の分泌を抑える薬としてプロトンポンプ阻害薬(PPI)またはボノプラザン(PCab)を服用するのが一般的です。これにより、食道へのダメージを防ぎ、炎症を改善することができます。また、生活習慣の改善も重要で、食後すぐに横にならない、食事量を調整する、刺激物を控えるといった工夫が効果的です。
機能性ディスペプシア:検査では異常なし?ストレス性胃痛の正体
 胃痛や吐き気が続くにもかかわらず、胃カメラや血液検査では異常が見つからない場合、「機能性ディスペプシア」が疑われます。これは、胃の動きが低下したり、過敏になったりすることで、慢性的な胃の不調が起こる病気です。
胃痛や吐き気が続くにもかかわらず、胃カメラや血液検査では異常が見つからない場合、「機能性ディスペプシア」が疑われます。これは、胃の動きが低下したり、過敏になったりすることで、慢性的な胃の不調が起こる病気です。
主な原因
この病気の原因は明確には分かっていませんが、ストレスや自律神経の乱れが大きく関与していると考えられています。ストレスが強いと、胃の動きが悪くなり、食べ物がスムーズに消化されず、胃もたれや吐き気が生じることがあります。また、胃酸の分泌が過剰になったり、逆に不足したりすることで、不快感が強くなることもあります。
症状の特徴
機能性ディスペプシアの主な症状は、食後の胃の不快感、胃もたれ、吐き気、みぞおちの痛みなどです。特に、ストレスがかかったときに症状が悪化しやすく、慢性的な胃の違和感を抱えている人が多いのが特徴です。
治療と対策
治療には、胃の動きを改善する薬(消化管運動機能改善薬)や胃酸を抑える薬が使われますが、ストレス管理が最も重要です。適度な運動、十分な睡眠、リラックスする時間を確保することで、自律神経を整え、胃の症状を改善することができます。また、カフェインやアルコールなど、胃を刺激するものを控えることも有効です。
胃がん:初期症状としての胃痛と吐き気に注意
胃痛や吐き気が続く場合、まれに胃がんが関係していることがあります。胃がんは、初期の段階ではほとんど自覚症状がないことが多いため、長引く胃の不調には注意が必要です。
主な原因とリスク要因
胃がんの発症には、ピロリ菌感染が大きく関与していることが分かっています。ピロリ菌が長期間にわたり胃の粘膜を刺激し、慢性的な炎症を引き起こすことで、がんのリスクが高まるとされています。また、喫煙や塩分の多い食事、飲酒などの生活習慣も発症リスクを高める要因となります。
症状の特徴
胃がんの初期症状は、胃もたれ、食欲不振、吐き気など、慢性胃炎と似た症状が多いため、見過ごされがちです。しかし、進行すると、みぞおちの痛みや、体重減少、貧血、黒色便(出血がある場合)などが現れることがあります。
検査と治療
胃がんを早期に発見するためには、定期的に胃カメラ検査を受けることが重要です。特に、ピロリ菌感染がある人や家族に胃がんの既往歴がある人は、定期的な検診を受けることをおすすめします。胃がんの治療は、がんの進行度によって異なりますが、早期に発見できれば、内視鏡治療や外科手術による摘出で完治する可能性が高いです。
胆石症や胆のう炎:胃痛と吐き気が胆のうの病気によることも
胃痛と吐き気が同時に起こる場合、実は胃ではなく「胆のう」に原因があることもあります。特に、胆石症や胆のう炎は、胃の痛みと間違われやすい病気のひとつです。胆のうは肝臓の下にある臓器で、食事の消化を助ける「胆汁」を貯蔵・分泌する役割を持っています。しかし、胆のう内に胆石ができると、胆汁の流れが悪くなり、炎症を引き起こすことがあります。
主な原因とリスク要因
 胆石症の原因としては、脂肪の多い食事、肥満、遺伝的要因、妊娠、ホルモンバランスの変化などが挙げられます。特に、高カロリーな食事が続くと、胆汁の成分が濃縮されやすくなり、胆石が形成されるリスクが高まります。また、胆のう炎は、胆石が胆のうの出口を塞いでしまうことで起こることが多いです。
胆石症の原因としては、脂肪の多い食事、肥満、遺伝的要因、妊娠、ホルモンバランスの変化などが挙げられます。特に、高カロリーな食事が続くと、胆汁の成分が濃縮されやすくなり、胆石が形成されるリスクが高まります。また、胆のう炎は、胆石が胆のうの出口を塞いでしまうことで起こることが多いです。
症状の特徴
胆石症や胆のう炎の典型的な症状として、右上腹部の激しい痛みが挙げられます。特に、脂っこい食事をした後に痛みが出ることが多く、痛みが肩や背中に放散することもあります。また、吐き気や嘔吐、発熱を伴うことがあり、炎症が悪化すると強い倦怠感や黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)などの症状が現れることもあります。
治療と対策
胆石症が軽度で症状がない場合は、特に治療をせず、経過観察を行うこともあります。しかし、胆のう炎を伴う場合は、抗生物質や痛み止めの投与が必要になり、重症化すると胆のうの摘出手術(胆のう摘出術)が行われることもあります。食生活の改善としては、脂肪の多い食事を避け、バランスの取れた食生活を心がけることが重要です。
膵炎:みぞおちの痛みと吐き気が続く場合に疑うべき疾患
膵炎は、膵臓(すいぞう)に炎症が起こる病気で、みぞおちの強い痛みと吐き気を引き起こすことがあります。膵臓は、消化酵素を分泌する臓器であり、正常な状態では食べ物の消化を助けます。しかし、膵炎になると、膵臓自体が自分の酵素で傷ついてしまい、強い炎症が生じます。
主な原因とリスク要因
 膵炎の原因としては、過度なアルコール摂取、胆石症、高脂血症(高中性脂肪血症)などが挙げられます。特に、大量の飲酒が続くと膵臓に負担がかかり、急性膵炎を引き起こすことがあります。また、胆石が膵管を塞ぐことで膵液が流れにくくなり、膵炎を発症するケースもあります。
膵炎の原因としては、過度なアルコール摂取、胆石症、高脂血症(高中性脂肪血症)などが挙げられます。特に、大量の飲酒が続くと膵臓に負担がかかり、急性膵炎を引き起こすことがあります。また、胆石が膵管を塞ぐことで膵液が流れにくくなり、膵炎を発症するケースもあります。
症状の特徴
膵炎の特徴的な症状は、みぞおちから背中にかけての激しい痛みです。痛みは持続的で、前かがみになると多少楽になることがあるのが特徴です。また、吐き気や嘔吐、発熱、食欲不振なども伴うことが多く、重症化すると血圧低下やショック状態になることもあります。
治療と対策
急性膵炎の場合、入院して絶食を行い、点滴で栄養を補給しながら膵臓を休ませる治療が必要になります。慢性膵炎の場合は、食生活の改善や禁酒が重要となります。膵炎を予防するためには、アルコールの過剰摂取を控え、脂肪分の多い食事を避けることが大切です。
腸閉塞(イレウス):胃痛と吐き気に加えてお腹が張る症状に注意
腸閉塞(イレウス)は、腸の中の内容物が通過できなくなる状態で、胃痛と吐き気が同時に現れることが多い病気です。腸の動きが止まったり、物理的に腸が塞がれたりすると、腸の中にガスや食べ物が溜まり、激しい腹痛や吐き気を引き起こします。
主な原因
 腸閉塞の原因には、手術後の癒着、腫瘍、ヘルニア、腸のねじれ(腸捻転)などがあります。また、高齢者では腸の動きが弱くなり、腸閉塞を起こしやすくなることもあります。
腸閉塞の原因には、手術後の癒着、腫瘍、ヘルニア、腸のねじれ(腸捻転)などがあります。また、高齢者では腸の動きが弱くなり、腸閉塞を起こしやすくなることもあります。
症状の特徴
腸閉塞の主な症状は、腹部の激しい痛み、吐き気・嘔吐、お腹の張りです。特に、食事をすると吐き気が強くなり、便やガスが出なくなるのが特徴です。症状が進行すると、腸が壊死する危険性があるため、早急な治療が必要になります。
治療と対策
腸閉塞の治療では、絶食を行い、腸の内容物を減らすための点滴治療を行うのが一般的です。場合によっては、鼻からチューブを入れて腸内のガスを排出する処置が行われることもあります。腸閉塞は放置すると重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、症状が疑われる場合はすぐに医療機関を受診することが重要です。
食中毒や感染性胃腸炎:突然の激しい症状の正体とは?
胃痛と吐き気が急激に現れた場合、食中毒や感染性胃腸炎が原因となっていることが多いです。特に、細菌やウイルスに感染すると、胃や腸が強く刺激され、腹痛、吐き気、下痢などの症状が同時に発生することがあります。
主な原因
 食中毒や感染性胃腸炎は、ウイルス(ノロウイルス、ロタウイルスなど)や細菌(サルモネラ菌、カンピロバクター、大腸菌など)による感染が主な原因です。感染源となるのは、不十分な加熱処理をした食品や汚染された水、生もの(刺身、寿司など)などです。
食中毒や感染性胃腸炎は、ウイルス(ノロウイルス、ロタウイルスなど)や細菌(サルモネラ菌、カンピロバクター、大腸菌など)による感染が主な原因です。感染源となるのは、不十分な加熱処理をした食品や汚染された水、生もの(刺身、寿司など)などです。
症状の特徴
症状は、突然の激しい胃痛、吐き気、嘔吐、下痢、発熱などが特徴です。特に、ウイルス性胃腸炎では水のような下痢が続き、脱水症状を引き起こすことがあるため、注意が必要です。
治療と対策
食中毒や感染性胃腸炎の治療では、水分補給を最優先し、体内の電解質バランスを維持することが重要です。特に、嘔吐や下痢がひどい場合は、経口補水液(OS-1など)をこまめに摂取し、脱水を防ぐようにします。細菌感染の場合は、抗生物質が処方されることもありますが、ウイルス性の場合は自然治癒を待つことがほとんどです。
心筋梗塞:胃痛と吐き気が隠れた心疾患のサインであることも
胃痛や吐き気は、胃の問題ではなく心臓の異常によって引き起こされることがあるため、注意が必要です。特に、心筋梗塞(しんきんこうそく)は、胃痛と間違われることがあり、見逃すと命に関わる重大な疾患です。
主な原因
 心筋梗塞は、心臓に血液を送る冠動脈が詰まり、心筋が壊死する病気です。動脈硬化、高血圧、糖尿病、喫煙などがリスク要因となります。
心筋梗塞は、心臓に血液を送る冠動脈が詰まり、心筋が壊死する病気です。動脈硬化、高血圧、糖尿病、喫煙などがリスク要因となります。
症状の特徴
心筋梗塞の症状は、胸の痛みが一般的ですが、場合によってはみぞおちの痛みや吐き気、冷や汗、息苦しさが主な症状として現れることがあります。特に、高齢者や糖尿病患者では、典型的な胸の痛みを感じにくいため、「胃が痛い」と訴えるケースもあります。
治療と対策
心筋梗塞の疑いがある場合は、一刻も早く救急車を呼び、適切な医療機関で治療を受けることが重要です。心疾患のリスクがある人は、定期的な健康診断を受け、血圧やコレステロール値を管理することが予防につながります。
ご予約はこちらから
当院では、胃カメラ検査をご検討の方に丁寧に診察と検査を行います。まずは、外来のご予約のうえご来院ください。胃カメラ希望でご来院される場合にはWebにて直接胃カメラのご予約も可能となっております。24時間web予約が可能です。