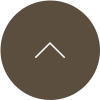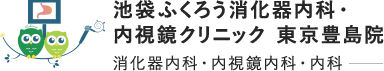「満員電車で胃が痛くなる…」ストレスと胃腸の密接な関係とは?



院長 柏木 宏幸所属学会・資格
- 日本内科学会 総合内科専門医
- 日本内科学会 内科認定医
- 日本消化器病学会 消化器病専門医
- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
- 一般社団法人日本病院総合診療医学会
認定病院総合診療医 - 難病指定医
- がん診療に関わる医師に対する緩和ケア 研修会 修了
- PEG・在宅医療研究会 修了証
- 満員電車で胃が痛くなるのはなぜ?ストレスと胃の関係
- 満員電車のストレスが腸にも影響を与える理由
- ストレスによる胃痛を防ぐための生活習慣
- 満員電車のストレスが胃腸だけでなく全身の健康を損なう理由
- 満員電車のストレスが「胃潰瘍」のリスクを高める理由
- 満員電車で急にお腹が痛くなる「過敏性腸症候群(IBS)」とは?
- ストレスによる「胃食道逆流症(GERD)」と満員電車の関係
- ストレスで胃腸の「血流」が低下し、栄養吸収が悪化する?
- 満員電車のストレスが「胆汁の分泌異常」を引き起こし、消化不良を悪化させる?
- 満員電車のストレスが「胃アレルギー」を引き起こす可能性
- 満員電車でストレスを感じると「胃酸過多」よりも「胃酸不足」が問題になる?
- ご予約はこちらから
通勤や通学の最中に胃が痛くなったことはありませんか?外来でお越し頂く患者さんの中には「通勤中に胃痛があったので外来を予約しました」、「出社したけど症状が改善しないので外来を予約して早退してきました」とおっしゃられる患者さんが日常いらっしゃいます。実は、満員電車で胃が痛くなるのは自律神経に原因があるのです。本記事では、満員電車と胃痛の関係性について詳しく解説し、解決策を紹介してまいります。
満員電車で胃が痛くなるのはなぜ?ストレスと胃の関係
 満員電車に乗ることで胃が痛くなるのは、単なる偶然ではなく、ストレスによって自律神経が乱れることが大きな要因です。私たちの体は、「交感神経」と「副交感神経」という二つの自律神経によってコントロールされています。交感神経は主に「緊張・興奮・ストレス」を感じるときに働き、心拍数を上げたり、血圧を上昇させたりする役割を持っています。一方、副交感神経は「リラックス・消化・休息」を担当し、胃腸の働きを促進する役割を持ちます。
満員電車に乗ることで胃が痛くなるのは、単なる偶然ではなく、ストレスによって自律神経が乱れることが大きな要因です。私たちの体は、「交感神経」と「副交感神経」という二つの自律神経によってコントロールされています。交感神経は主に「緊張・興奮・ストレス」を感じるときに働き、心拍数を上げたり、血圧を上昇させたりする役割を持っています。一方、副交感神経は「リラックス・消化・休息」を担当し、胃腸の働きを促進する役割を持ちます。
交感神経が優位になる

満員電車のようなストレス環境では、交感神経が優位になり、胃腸の働きが抑制されます。通常、食べ物が胃に入ると副交感神経が働き、胃酸が分泌され、蠕動運動(食べ物を消化するための胃の動き)が活発になります。しかし、ストレスを感じると交感神経が優位になり、胃の動きが鈍くなり、胃酸の分泌が乱れます。これにより、消化がスムーズに行われなくなり、胃痛や胃もたれを引き起こすのです。
また、ストレスを感じると、体は「コルチゾール」や「アドレナリン」といったホルモンを分泌します。これらのホルモンは短期的には体をストレスから守る役割を果たしますが、長期間にわたって分泌が続くと、胃の粘膜を傷つけ、胃炎や胃潰瘍の原因になります。そのため、満員電車のストレスを毎日のように受けていると、慢性的な胃痛に悩まされる可能性が高くなるのです。
満員電車のストレスが腸にも影響を与える理由
 満員電車のストレスは、胃だけでなく腸にも悪影響を及ぼします。これは、ストレスが「脳腸相関(のうちょうそうかん)」と呼ばれる仕組みを通じて腸の働きを乱すためです。脳腸相関とは、脳と腸が密接に連携していることを指し、ストレスを感じると腸の動きが変化することが分かっています。
満員電車のストレスは、胃だけでなく腸にも悪影響を及ぼします。これは、ストレスが「脳腸相関(のうちょうそうかん)」と呼ばれる仕組みを通じて腸の働きを乱すためです。脳腸相関とは、脳と腸が密接に連携していることを指し、ストレスを感じると腸の動きが変化することが分かっています。
腸の蠕動運動の異常
 ストレスが腸に与える影響は主に2つあります。1つ目は「腸の蠕動運動の異常」です。ストレスを受けると腸の動きが過剰に活発になり、下痢を引き起こすことがあります。逆に、腸の動きが鈍くなりすぎると、便秘の原因になります。満員電車に乗ると急にお腹が痛くなったり、緊張すると便秘になりやすくなったりするのは、ストレスが腸の動きを乱しているからなのです。
ストレスが腸に与える影響は主に2つあります。1つ目は「腸の蠕動運動の異常」です。ストレスを受けると腸の動きが過剰に活発になり、下痢を引き起こすことがあります。逆に、腸の動きが鈍くなりすぎると、便秘の原因になります。満員電車に乗ると急にお腹が痛くなったり、緊張すると便秘になりやすくなったりするのは、ストレスが腸の動きを乱しているからなのです。
腸内環境の悪化
 2つ目は「腸内環境の悪化」です。腸には数百兆個もの腸内細菌が存在し、善玉菌・悪玉菌・日和見菌のバランスによって健康が保たれています。しかし、ストレスがかかると悪玉菌が増え、腸内環境が乱れやすくなります。これにより、ガスの発生が増えたり、腸の炎症が起こりやすくなったりして、腹痛や膨満感(お腹の張り)を感じることが多くなります。
2つ目は「腸内環境の悪化」です。腸には数百兆個もの腸内細菌が存在し、善玉菌・悪玉菌・日和見菌のバランスによって健康が保たれています。しかし、ストレスがかかると悪玉菌が増え、腸内環境が乱れやすくなります。これにより、ガスの発生が増えたり、腸の炎症が起こりやすくなったりして、腹痛や膨満感(お腹の張り)を感じることが多くなります。
ストレスによる胃痛を防ぐための生活習慣
食生活の見直し
 ストレスが原因で胃が痛くなるのを防ぐためには、日常生活の中でストレスを和らげる習慣を取り入れることが重要です。まず、食生活の見直しが必要です。ストレスがかかると胃の粘膜が弱くなるため、刺激の強い食べ物(辛いもの、酸っぱいもの、カフェイン、アルコールなど)は控えることが大切です。代わりに、胃に優しい食べ物(ヨーグルト、納豆、温野菜、白身魚など)を意識的に摂ることで、胃の負担を軽減できます。
ストレスが原因で胃が痛くなるのを防ぐためには、日常生活の中でストレスを和らげる習慣を取り入れることが重要です。まず、食生活の見直しが必要です。ストレスがかかると胃の粘膜が弱くなるため、刺激の強い食べ物(辛いもの、酸っぱいもの、カフェイン、アルコールなど)は控えることが大切です。代わりに、胃に優しい食べ物(ヨーグルト、納豆、温野菜、白身魚など)を意識的に摂ることで、胃の負担を軽減できます。
ストレス緩和
 また、満員電車のストレスを軽減するために、乗車時間をずらす、座れる電車を選ぶ、リラックスできる音楽を聴くなどの工夫も効果的です。特に、通勤前に軽くストレッチをすることで、体の緊張をほぐし、ストレス耐性を高めることができます。
また、満員電車のストレスを軽減するために、乗車時間をずらす、座れる電車を選ぶ、リラックスできる音楽を聴くなどの工夫も効果的です。特に、通勤前に軽くストレッチをすることで、体の緊張をほぐし、ストレス耐性を高めることができます。
リラックス
 呼吸法を取り入れることも有効です。ストレスを感じると呼吸が浅くなりやすいため、意識的に深呼吸を行い、副交感神経を優位にすることで、胃の負担を軽減することができます。特に、4秒かけて鼻から息を吸い、8秒かけてゆっくり口から吐く「腹式呼吸」は、リラックス効果が高く、胃腸の調子を整えるのに役立ちます。
呼吸法を取り入れることも有効です。ストレスを感じると呼吸が浅くなりやすいため、意識的に深呼吸を行い、副交感神経を優位にすることで、胃の負担を軽減することができます。特に、4秒かけて鼻から息を吸い、8秒かけてゆっくり口から吐く「腹式呼吸」は、リラックス効果が高く、胃腸の調子を整えるのに役立ちます。
満員電車のストレスが胃腸だけでなく全身の健康を損なう理由
 満員電車によるストレスは、胃や腸だけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。ストレスが長期間続くと、自律神経が乱れ、心身のバランスが崩れることで、さまざまな不調が現れます。特に、ストレスがかかると「交感神経」が優位になりやすく、血管が収縮して血流が悪化します。その結果、体が冷えやすくなり、免疫力の低下を引き起こします。
満員電車によるストレスは、胃や腸だけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。ストレスが長期間続くと、自律神経が乱れ、心身のバランスが崩れることで、さまざまな不調が現れます。特に、ストレスがかかると「交感神経」が優位になりやすく、血管が収縮して血流が悪化します。その結果、体が冷えやすくなり、免疫力の低下を引き起こします。
睡眠の質にも悪影響
 慢性的なストレスは睡眠の質にも悪影響を与えます。ストレスによって交感神経が過度に刺激されると、夜になってもリラックスできず、寝つきが悪くなったり、浅い眠りが続いたりすることがあります。睡眠不足になると、胃腸の回復力が低下し、胃の痛みや消化不良がさらに悪化する悪循環に陥ることもあります。
慢性的なストレスは睡眠の質にも悪影響を与えます。ストレスによって交感神経が過度に刺激されると、夜になってもリラックスできず、寝つきが悪くなったり、浅い眠りが続いたりすることがあります。睡眠不足になると、胃腸の回復力が低下し、胃の痛みや消化不良がさらに悪化する悪循環に陥ることもあります。
肌荒れ、頭痛、肩こり
 ストレスホルモンである「コルチゾール」の過剰分泌は、体内の炎症を引き起こし、肌荒れや頭痛、肩こりといった不調の原因にもなります。満員電車のストレスが毎日積み重なることで、胃腸だけでなく、全身の健康が損なわれてしまう可能性があるのです。そのため、日頃からストレスを和らげる習慣を取り入れることが、健康維持には欠かせません。
ストレスホルモンである「コルチゾール」の過剰分泌は、体内の炎症を引き起こし、肌荒れや頭痛、肩こりといった不調の原因にもなります。満員電車のストレスが毎日積み重なることで、胃腸だけでなく、全身の健康が損なわれてしまう可能性があるのです。そのため、日頃からストレスを和らげる習慣を取り入れることが、健康維持には欠かせません。
満員電車のストレスが「胃潰瘍」のリスクを高める理由
 ストレスが強い環境にさらされると、「胃潰瘍(いかいよう)」のリスクが高まることが知られています。胃潰瘍とは、胃酸や消化酵素によって胃の粘膜が傷つき、深い潰瘍が形成される疾患です。満員電車のような強いストレス環境では、胃酸の分泌が過剰になり、胃の粘膜を守る防御機能が低下するため、潰瘍のリスクが高まります。
ストレスが強い環境にさらされると、「胃潰瘍(いかいよう)」のリスクが高まることが知られています。胃潰瘍とは、胃酸や消化酵素によって胃の粘膜が傷つき、深い潰瘍が形成される疾患です。満員電車のような強いストレス環境では、胃酸の分泌が過剰になり、胃の粘膜を守る防御機能が低下するため、潰瘍のリスクが高まります。
ストレス性潰瘍(急性胃粘膜病変)
ストレスが胃潰瘍を引き起こすメカニズムとして、「ストレス性潰瘍(急性胃粘膜病変)」が挙げられます。これは、交感神経が活性化することで胃粘膜の血流が低下し、粘膜の修復機能が弱まることで発生します。特に、長期間にわたってストレスを受け続けると、胃酸の分泌がコントロールできなくなり、慢性的な胃炎や潰瘍を引き起こす可能性が高くなります。
胃潰瘍は悪化すると出血を伴い、黒色便や吐血を引き起こすこともあります。満員電車のストレスを軽減し、胃の健康を守るためには、食生活の改善や適切なストレス対策が重要です。
満員電車で急にお腹が痛くなる「過敏性腸症候群(IBS)」とは?
 満員電車に乗ると突然お腹が痛くなり、トイレに行きたくなる人は、「過敏性腸症候群(IBS)」の可能性があります。IBSは、腸に明確な異常がないにもかかわらず、腹痛や下痢・便秘などの症状を引き起こす疾患です。特に、ストレスがIBSの発症や悪化の大きな要因となることが分かっています。
満員電車に乗ると突然お腹が痛くなり、トイレに行きたくなる人は、「過敏性腸症候群(IBS)」の可能性があります。IBSは、腸に明確な異常がないにもかかわらず、腹痛や下痢・便秘などの症状を引き起こす疾患です。特に、ストレスがIBSの発症や悪化の大きな要因となることが分かっています。
IBSのメカニズム

IBSのメカニズムとしては、腸の運動異常や知覚過敏、脳腸相関の異常が関与しています。ストレスを感じると交感神経が優位になり、腸の動きが不規則になります。これにより、腸が過剰に収縮し、腹痛や下痢を引き起こすことがあります。逆に、腸の動きが鈍くなると、便秘の症状が現れます。満員電車でIBSの症状を和らげるためには、事前に消化の良い食事を摂る、整腸剤を服用する、電車に乗る前に深呼吸をしてリラックスするなどの対策が有効です。
ストレスによる「胃食道逆流症(GERD)」と満員電車の関係
胃食道逆流症(GERD)
 満員電車でストレスを感じたとき、「胃がムカムカする」「酸っぱいものがこみ上げてくる」といった経験はありませんか?これは、「胃食道逆流症(GERD)」の症状かもしれません。GERDは、胃酸が食道に逆流し、胸やけや喉の違和感を引き起こす病気です。
満員電車でストレスを感じたとき、「胃がムカムカする」「酸っぱいものがこみ上げてくる」といった経験はありませんか?これは、「胃食道逆流症(GERD)」の症状かもしれません。GERDは、胃酸が食道に逆流し、胸やけや喉の違和感を引き起こす病気です。
胃酸の分泌過多
 ストレスがかかると、胃酸の分泌が増加するとともに、食道と胃の境界にある「下部食道括約筋」が緩みやすくなります。この筋肉が正常に機能しないと、胃酸が逆流しやすくなり、胸やけやゲップ、慢性的な咳などの症状が現れます。
ストレスがかかると、胃酸の分泌が増加するとともに、食道と胃の境界にある「下部食道括約筋」が緩みやすくなります。この筋肉が正常に機能しないと、胃酸が逆流しやすくなり、胸やけやゲップ、慢性的な咳などの症状が現れます。
満員電車のような長時間のストレス環境では、この症状が悪化しやすくなります。食後すぐに満員電車に乗ると、胃が圧迫されて胃酸の逆流が促されるため、GERDの症状が強く出ることもあります。満員電車でのGERD対策としては、食後1~2時間は電車に乗るのを避ける、ベルトや服を締めすぎない、胃酸を抑える薬を活用するなどの方法が有効です。
ストレスで胃腸の「血流」が低下し、栄養吸収が悪化する?
 満員電車のストレスは、胃腸の血流を低下させ、消化吸収の効率を下げることが分かっています。通常、食後は副交感神経が優位になり、胃腸の血流が増加し、消化がスムーズに進みます。しかし、ストレスによって交感神経が優位になると、胃腸の血流が制限され、消化機能が低下します。
満員電車のストレスは、胃腸の血流を低下させ、消化吸収の効率を下げることが分かっています。通常、食後は副交感神経が優位になり、胃腸の血流が増加し、消化がスムーズに進みます。しかし、ストレスによって交感神経が優位になると、胃腸の血流が制限され、消化機能が低下します。
食後のリラックスも大切に

この影響で、食べたものが十分に消化されず、胃もたれや腹痛を引き起こすだけでなく、栄養の吸収も妨げられます。特に、鉄分やビタミンB群の吸収が低下すると、貧血や疲労感、肌荒れといった症状が現れやすくなります。満員電車のストレスによる消化不良を防ぐためには、食後にリラックスする時間を確保し、胃腸の血流を改善することが重要です。
満員電車のストレスが「胆汁の分泌異常」を引き起こし、消化不良を悪化させる?
 満員電車のストレスが続くと、胃だけでなく「胆汁(たんじゅう)」の分泌にも悪影響を与えることが分かっています。胆汁は肝臓で作られ、脂肪の消化を助ける働きを持っていますが、ストレスによって自律神経のバランスが乱れると、その分泌が不安定になります。
満員電車のストレスが続くと、胃だけでなく「胆汁(たんじゅう)」の分泌にも悪影響を与えることが分かっています。胆汁は肝臓で作られ、脂肪の消化を助ける働きを持っていますが、ストレスによって自律神経のバランスが乱れると、その分泌が不安定になります。
 特に、交感神経が優位になると胆嚢(たんのう)の収縮が弱まり、胆汁がスムーズに分泌されなくなります。これにより、脂肪の消化が不十分になり、胃もたれや腹部膨満感(お腹の張り)、下痢を引き起こすことがあります。また、胆汁の分泌が低下すると、腸内の悪玉菌が増殖しやすくなり、腸内環境の悪化にもつながります。
特に、交感神経が優位になると胆嚢(たんのう)の収縮が弱まり、胆汁がスムーズに分泌されなくなります。これにより、脂肪の消化が不十分になり、胃もたれや腹部膨満感(お腹の張り)、下痢を引き起こすことがあります。また、胆汁の分泌が低下すると、腸内の悪玉菌が増殖しやすくなり、腸内環境の悪化にもつながります。
胆汁の分泌を正常に保つためには、ストレスを軽減するだけでなく、食事のタイミングや内容にも気を配ることが重要です。特に、食事を抜くと胆汁の流れが悪くなるため、朝食をしっかりと摂ることが胆汁の分泌を正常に保つのに役立ちます。
満員電車のストレスが「胃アレルギー」を引き起こす可能性
 「胃アレルギー」という言葉はあまり馴染みがないかもしれませんが、最近の研究では、ストレスが胃の免疫反応を過剰にし、食物アレルギーのような症状を引き起こすことが分かっています。通常、胃の粘膜は食べ物をしっかり消化し、体に必要な栄養を吸収する役割を担っています。しかし、満員電車のような強いストレス環境にいると、胃の粘膜に炎症が起こり、食物タンパク質を異物と認識してしまうことがあります。この状態になると、食後に胃痛や吐き気、胃もたれが起こりやすくなります。
「胃アレルギー」という言葉はあまり馴染みがないかもしれませんが、最近の研究では、ストレスが胃の免疫反応を過剰にし、食物アレルギーのような症状を引き起こすことが分かっています。通常、胃の粘膜は食べ物をしっかり消化し、体に必要な栄養を吸収する役割を担っています。しかし、満員電車のような強いストレス環境にいると、胃の粘膜に炎症が起こり、食物タンパク質を異物と認識してしまうことがあります。この状態になると、食後に胃痛や吐き気、胃もたれが起こりやすくなります。
胃痛や胃酸の過剰分泌を招くこと

特に、ストレスがかかると「マスト細胞(肥満細胞)」が活性化し、ヒスタミンが過剰に分泌されることが知られています。ヒスタミンはアレルギー症状を引き起こす物質で、胃の粘膜を刺激し、胃痛や胃酸の過剰分泌を招くことがあります。このような症状が続く場合は、ストレス管理を意識するだけでなく、ヒスタミンを多く含む食品(チーズ、ワイン、発酵食品など)を一時的に控えることで、胃の負担を軽減できる可能性があります。
満員電車のストレスが「胃アレルギー」を引き起こす可能性
 「胃アレルギー」という言葉はあまり馴染みがないかもしれませんが、最近の研究では、ストレスが胃の免疫反応を過剰にし、食物アレルギーのような症状を引き起こすことが分かっています。通常、胃の粘膜は食べ物をしっかり消化し、体に必要な栄養を吸収する役割を担っています。しかし、満員電車のような強いストレス環境にいると、胃の粘膜に炎症が起こり、食物タンパク質を異物と認識してしまうことがあります。この状態になると、食後に胃痛や吐き気、胃もたれが起こりやすくなります。
「胃アレルギー」という言葉はあまり馴染みがないかもしれませんが、最近の研究では、ストレスが胃の免疫反応を過剰にし、食物アレルギーのような症状を引き起こすことが分かっています。通常、胃の粘膜は食べ物をしっかり消化し、体に必要な栄養を吸収する役割を担っています。しかし、満員電車のような強いストレス環境にいると、胃の粘膜に炎症が起こり、食物タンパク質を異物と認識してしまうことがあります。この状態になると、食後に胃痛や吐き気、胃もたれが起こりやすくなります。
胃痛や胃酸の過剰分泌を招くこと

特に、ストレスがかかると「マスト細胞(肥満細胞)」が活性化し、ヒスタミンが過剰に分泌されることが知られています。ヒスタミンはアレルギー症状を引き起こす物質で、胃の粘膜を刺激し、胃痛や胃酸の過剰分泌を招くことがあります。このような症状が続く場合は、ストレス管理を意識するだけでなく、ヒスタミンを多く含む食品(チーズ、ワイン、発酵食品など)を一時的に控えることで、胃の負担を軽減できる可能性があります。
満員電車でストレスを感じると「胃酸過多」よりも「胃酸不足」が問題になる?
 ストレスがかかると「胃酸が過剰に分泌される」と思われがちですが、実際には「胃酸不足(低胃酸症)」の状態に陥ることも少なくありません。満員電車のストレスによって交感神経が過剰に働くと、胃の機能が抑制され、胃酸の分泌が減少することがあります。胃酸が不足すると、食べ物が十分に消化されず、胃もたれや膨満感が発生しやすくなります。また、胃酸には殺菌作用があるため、不足すると腸内に悪玉菌が増えやすくなり、下痢や便秘を引き起こすこともあります。さらに、胃酸が少ないと鉄分やビタミンB12の吸収が悪くなり、貧血や倦怠感を感じることもあります。
ストレスがかかると「胃酸が過剰に分泌される」と思われがちですが、実際には「胃酸不足(低胃酸症)」の状態に陥ることも少なくありません。満員電車のストレスによって交感神経が過剰に働くと、胃の機能が抑制され、胃酸の分泌が減少することがあります。胃酸が不足すると、食べ物が十分に消化されず、胃もたれや膨満感が発生しやすくなります。また、胃酸には殺菌作用があるため、不足すると腸内に悪玉菌が増えやすくなり、下痢や便秘を引き起こすこともあります。さらに、胃酸が少ないと鉄分やビタミンB12の吸収が悪くなり、貧血や倦怠感を感じることもあります。
 胃酸が不足すると、食べ物が十分に消化されず、胃もたれや膨満感が発生しやすくなります。また、胃酸には殺菌作用があるため、不足すると腸内に悪玉菌が増えやすくなり、下痢や便秘を引き起こすこともあります。さらに、胃酸が少ないと鉄分やビタミンB12の吸収が悪くなり、貧血や倦怠感を感じることもあります。胃酸不足を改善するためには、食事の際にしっかり噛んで唾液を出すことや、レモン水やリンゴ酢などの「胃酸の分泌を助ける食品」を取り入れることが有効です。また、ストレスを軽減し、副交感神経を活性化させることで、胃酸の分泌を正常に戻すことも重要です。
胃酸が不足すると、食べ物が十分に消化されず、胃もたれや膨満感が発生しやすくなります。また、胃酸には殺菌作用があるため、不足すると腸内に悪玉菌が増えやすくなり、下痢や便秘を引き起こすこともあります。さらに、胃酸が少ないと鉄分やビタミンB12の吸収が悪くなり、貧血や倦怠感を感じることもあります。胃酸不足を改善するためには、食事の際にしっかり噛んで唾液を出すことや、レモン水やリンゴ酢などの「胃酸の分泌を助ける食品」を取り入れることが有効です。また、ストレスを軽減し、副交感神経を活性化させることで、胃酸の分泌を正常に戻すことも重要です。
ご予約はこちらから
当院では、胃もたれでお悩みの方に丁寧に診察と検査を行います。場合によっては、内視鏡検査のご提案もいたします。外来、内視鏡検査はいずれも24時間web予約が可能です。