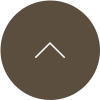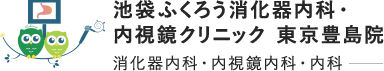「夜中に何度もトイレへ…」年齢とともに増える腸のトラブルとは?



院長 柏木 宏幸所属学会・資格
- 日本内科学会 総合内科専門医
- 日本内科学会 内科認定医
- 日本消化器病学会 消化器病専門医
- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
- 一般社団法人日本病院総合診療医学会
認定病院総合診療医 - 難病指定医
- がん診療に関わる医師に対する緩和ケア 研修会 修了
- PEG・在宅医療研究会 修了証
「夜中に何度もトイレに行きたくなる…」「寝ている間に排便のために目が覚める…」といった症状に悩んでいませんか?特に年齢を重ねるにつれて、このような症状が増えると感じる人が多いのは事実です。
多くの人は「夜中に何度も起きる=膀胱や前立腺の問題」と考えがちですが、実は腸の働きも関係していることが少なくありません。加齢とともに腸の機能が変化し、夜間に排便のトラブルが起こりやすくなるのです。
本記事では、年齢とともに変化する腸の働きや、夜中のトイレが増える原因、改善策について詳しく解説していきます。
腸の働きは年齢とともにどう変化するのか?
加齢とともに腸の働きにはさまざまな変化が起こります。特に影響を受けるのが、腸のぜん動運動(内容物を送る動き)と腸内フローラ(腸内細菌のバランス)です。
①腸の動きの変化
若い頃はスムーズに行われていた腸のぜん動運動も、年齢を重ねると徐々に低下します。その結果、食べたものが腸内に長くとどまり、便秘になりやすくなるのです。便秘が続くと腸内でガスが発生し、夜間に腹部膨満感を感じて目が覚めることがあります。
一方で、腸のぜん動運動が不規則になると、食べたものが急速に排出されることもあります。これにより、夜中に急に下痢になったり、便意を感じて目が覚めることもあるのです。
②腸内フローラの変化
腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌という3種類の細菌が存在しています。加齢とともに善玉菌が減少し、悪玉菌が優勢になると、腸内環境が乱れやすくなります。その結果、便秘や下痢が頻繁に起こり、夜間にトイレへ行く回数が増えるのです。
このように、年齢とともに腸の働きが変化することで、夜中のトイレの回数が増える要因となっているのです。
夜間頻尿と腸の関係:排便トラブルが影響することも
夜間に何度もトイレに行く場合、多くの人は「膀胱や前立腺の問題」と考えがちですが、実は腸の影響も無視できません。特に便秘が続くと、大腸の膨張によって膀胱が圧迫され、頻尿の原因になることがあります。
便秘と夜間頻尿の関係
便秘がひどくなると、腸内に溜まった便が膀胱を圧迫し、尿を溜められるスペースが減ることで、夜間の尿意が増えることがあります。また、便秘によるガスの発生も腸を膨張させ、膀胱への圧力を強めることがあるのです。
特に、寝る前に膨満感を感じる場合は、腸のガスが影響している可能性が高いでしょう。ガスがたまると、腸の動きが活発になり、夜間にトイレに行きたくなることがあります。
このように、便秘や腸内ガスの影響が、夜間頻尿の原因になっている可能性があるため、腸の健康を整えることが重要です。
加齢とともに起こりやすい腸のトラブルとは?
 年齢を重ねると、腸の働きが不安定になり、さまざまな腸のトラブルが起こりやすくなります。特に、以下のような症状がある場合、夜間のトイレ回数が増える原因になっている可能性があります。
年齢を重ねると、腸の働きが不安定になり、さまざまな腸のトラブルが起こりやすくなります。特に、以下のような症状がある場合、夜間のトイレ回数が増える原因になっている可能性があります。
① 慢性便秘
加齢により腸のぜん動運動が低下し、便秘になりやすくなります。特に、水分摂取不足や運動不足が重なると、さらに排便が困難になることがあります。
② 過敏性腸症候群(IBS)
ストレスや腸内環境の乱れによって、腸が過剰に反応し、下痢や便秘を繰り返すことがあります。特に、夜間に急な下痢が起こるタイプのIBSは、睡眠の質を低下させる原因になります。
③ 直腸性便秘
高齢者に多い便秘の一種で、直腸に便が溜まりやすくなります。このタイプの便秘は、夜間に突然便意を感じて目が覚めることが特徴です。
④ 腸内フローラの乱れ
加齢により腸内の善玉菌が減少し、悪玉菌が優勢になると、腸の働きが不安定になり、夜間に便意を催すことが増えます。
⑤ 炎症性腸疾患(IBD)
クローン病や潰瘍性大腸炎を総称して炎症性腸疾患(IBD)と言います。炎症性腸疾患の患者さんでは、夜間に下痢や腹痛が発生しやすくなります。特に、頻繁に夜間トイレに行く場合は、消化器内科での診断が必要です。若い人に発症しやすい疾患です。
このように、加齢による腸のトラブルが、夜間のトイレの回数を増やす原因になっている可能性があります。
便秘と夜間のトイレの関係!なぜ寝る前に便意が?
 「日中は便意を感じなかったのに、寝る直前や夜中に便意が出る」という経験はありませんか?これは、腸の働きが夜間に活発になることが原因です。特に、便秘傾向の人は、昼間に排便できなかった便が夜間に腸内で動き、急に便意を感じることがあります。
「日中は便意を感じなかったのに、寝る直前や夜中に便意が出る」という経験はありませんか?これは、腸の働きが夜間に活発になることが原因です。特に、便秘傾向の人は、昼間に排便できなかった便が夜間に腸内で動き、急に便意を感じることがあります。
夜間の便意が起こる原因
①腸のぜん動運動の遅れ
- 日中に腸があまり動かず、夜になってやっと動き出すことで便意が生じる。
- 座りっぱなしや運動不足の人は、日中の腸の活動が低下しやすい。
②副交感神経の働きが強まる
- 夜になるとリラックスモードの副交感神経が優位になり、腸の活動が活発になる。
- 特に、ストレスが多い人は日中に腸の働きが抑制され、夜になって急に腸が動き出すことがある。
③腸内ガスの影響
- 便秘で腸内にガスが溜まると、腸が刺激され、夜間に便意が出やすくなる。
- 特に、発酵食品や食物繊維の摂取が多すぎると、夜間の腸の動きを促進しやすい。
④遅い時間の食事
- 寝る直前に食事をすると、消化活動が遅れ、夜間に腸が動き始めることがある。
- 夕食の時間が遅い人ほど、夜間の便意が起こりやすい。
便秘による夜間のトイレを防ぐ方法
- 夕食は就寝3時間前までに済ませる(消化のタイミングを調整)
- 日中の適度な運動を増やす(腸の活動を促進する)
- 水分をこまめに摂取する(腸内の便を柔らかくする)
- ストレス管理を意識する(自律神経を整える)
便秘による夜間の便意を減らすためには、日中の腸の活動を正常にすることが重要です。
下痢が夜中に起こる原因!過敏性腸症候群との関連
 便秘とは逆に、「夜中に突然下痢をする」「就寝中に腹痛で目が覚める」という症状に悩んでいる人もいます。これは、腸の過剰な活動や腸内環境の乱れが原因になっていることが多いです。
便秘とは逆に、「夜中に突然下痢をする」「就寝中に腹痛で目が覚める」という症状に悩んでいる人もいます。これは、腸の過剰な活動や腸内環境の乱れが原因になっていることが多いです。
夜間に下痢が起こる主な原因
①過敏性腸症候群(IBS)
- ストレスや腸内環境の乱れにより、腸が過剰に反応する病気。
- 特に、「下痢型IBS」の人は、寝ている間でも腸の動きが活発になり、突然の下痢を引き起こすことがある。
②腸内フローラの乱れ
- 善玉菌が減少し、腸のバランスが崩れると、腸が過敏になりやすい。
- 特に、高脂肪食や加工食品を頻繁に食べる人は、腸内細菌のバランスが悪化しやすい。
③食物不耐症(乳糖不耐症・グルテン不耐症)
- 牛乳やパンを食べると、夜中に下痢が起こる場合は、食物不耐症の可能性。
- 特に乳糖不耐症の人は、夕食に乳製品を摂ると、夜中に腸が過剰に働くことがある。
④感染性腸炎(ウイルス・細菌感染)
- 食中毒やウイルス性腸炎の初期症状として、夜間の突然の下痢が起こることがある。
- 発熱や吐き気を伴う場合は、早めの受診が必要。
⑤ 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)
- 日中だけでなく夜間に下痢や腹痛が発生しやすくなる。
- 若い人に発症しやすい疾患であることから、下痢症状が長く続く場合には消化器内科への受診が必要。
夜間の下痢を防ぐ方法
- 食事の見直し(刺激物を控える)
- 腸に優しい食品(発酵食品)を摂る
- ストレス管理を徹底し、腸を安定させる
下痢が続く場合は、腸内環境の改善や食生活の見直しが必要になります。
腸内フローラの変化と夜間のトイレの関係
腸内フローラ(腸内細菌叢)は、人間の消化活動や腸の働きに大きな影響を与えています。加齢とともに腸内フローラが変化すると、腸の働きが不安定になり、夜間に排便のために目が覚める回数が増えることがあります。
加齢による腸内フローラの変化
腸内には、善玉菌(ビフィズス菌・乳酸菌)、悪玉菌(ウェルシュ菌・大腸菌)、そして日和見菌(どちらにもなりうる細菌)の3種類の細菌がバランスを保ちながら共存しています。しかし、加齢によって善玉菌が減少し、悪玉菌が増えやすくなることがわかっています。
特に、加齢に伴い腸の働きが鈍ると、腸内環境の悪化が進みやすくなり、以下のような影響が出てきます。
①便秘や下痢の頻度が増加する
善玉菌が減ることで、腸の働きをスムーズにする短鎖脂肪酸の産生が減少し、腸の動きが不安定になる。
②腸内ガスの増加
腸内フローラのバランスが崩れると、発酵が過剰になり、ガスが発生しやすくなる。これにより、夜間の腹部膨満感や便意を引き起こすことがある。
③腸の過敏性が高まる
腸内環境の悪化が進むと、腸の粘膜が過敏になり、通常なら問題ない食事や飲み物にも反応しやすくなる。その結果、夜間に突然便意を感じることがある。
腸内フローラを改善し、夜間のトイレを減らす方法
腸内フローラを整えるためには、腸に良い食生活や生活習慣を取り入れることが重要です。
- 発酵食品(ヨーグルト、納豆、味噌、キムチなど)を積極的に摂ることで、腸内の善玉菌を増やす。
- 水溶性食物繊維(オートミール、わかめ、リンゴなど)を摂取することで、腸内環境を改善し、便通を安定させる。
- 夜間の排便を防ぐために、就寝3時間前には食事を済ませることで、腸の過活動を抑える。
腸内フローラが整うと、腸の働きが正常化し、夜中に急にトイレへ行きたくなる回数を減らすことができるのです。
自律神経の乱れが腸の働きを夜間に活発にさせる?
「日中は特に問題がないのに、夜になると突然お腹がゴロゴロし始める」「寝ている途中に急な便意を感じ、何度もトイレに行く」といった経験がある人は少なくありません。こうした夜間の腸の過活動には、自律神経の乱れが大きく関係していると考えられています。
自律神経と腸の関係
自律神経は、交感神経(活動モード)と副交感神経(リラックスモード)の2つの神経から構成されており、これらがバランスを取りながら腸の働きをコントロールしています。
日中は、仕事や家事などの活動により交感神経が優位になり、腸の動きは抑えられる傾向にあります。しかし、夜になると副交感神経が優位になり、腸のぜん動運動が活発になります。これは正常な生理現象ですが、自律神経のバランスが崩れていると、この切り替えがうまくいかず、腸が夜間に過剰に活動してしまうことがあるのです。
特に、ストレスが多い人や、不規則な生活を送っている人は、自律神経のリズムが乱れやすく、腸の働きが夜間に活発になりやすいと言われています。
自律神経の乱れが腸の働きを過剰にする仕組み
①日中に腸の活動が抑えられる
強いストレスや忙しさによって交感神経が過剰に働くと、腸のぜん動運動が抑制され、便意を感じにくくなります。これにより、日中に本来排泄されるべき便が腸内にとどまり、夜間に腸の活動が再び活発になったときに便意を感じるようになります。
②夜間に急激に副交感神経が優位になる
日中に抑制されていた腸の動きが、夜間に急に活発になることで、腸が過剰に動き始め、強い便意や腹痛を伴うことがあります。特に、ストレスや緊張が強かった日ほど、この現象が顕著に現れることがあります。
③腸が過敏になり、少しの刺激でトイレに行きたくなる
自律神経の乱れが続くと、腸の感覚が過敏になり、通常なら気にならない程度の腸の動きでも、便意として感じやすくなります。これは、「過敏性腸症候群(IBS)」の症状にも似ており、特にストレスが強い人ほど夜間に腸の活動が過剰になりやすくなります。
夜間の腸の活動を落ち着かせる方法
夜間のトイレ回数を減らすためには、自律神経のバランスを整え、腸の働きを正常化することが重要です。そのために、以下のような生活習慣の改善が効果的です。
① 寝る前にリラックスする時間を作る
寝る直前まで仕事をしたり、スマホやパソコンの画面を見続けたりすると、交感神経が優位になり、副交感神経への切り替えがスムーズに行われません。寝る1時間前は、リラックスできる音楽を聴く、読書をする、ぬるめのお風呂に入るなど、心を落ち着かせる時間を作ることが大切です。
② 就寝前のカフェイン・アルコールを避ける
コーヒーや紅茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、交感神経を刺激し、腸の活動を促進するため、寝る前の摂取は避けるべきです。また、アルコールは一時的にリラックス効果があるものの、睡眠の質を低下させ、夜間の腸の活動を乱す可能性があるため、寝る前の飲酒は控えることが望ましいでしょう。
③ 睡眠のリズムを一定に保つ
不規則な睡眠習慣は自律神経のバランスを崩し、腸のリズムを乱します。毎日同じ時間に就寝し、同じ時間に起きることで、自律神経の働きを安定させ、腸のぜん動運動を正常化することができます。
④ 深呼吸や軽いストレッチを行う
深呼吸やヨガ、軽いストレッチは、副交感神経を優位にし、腸の過剰な活動を抑える効果があります。寝る前に腹式呼吸を取り入れることで、腸の動きを穏やかにし、夜間の便意を減らすことができます。
自律神経を整えることで、腸のリズムも安定する
腸の活動は自律神経によって調整されているため、自律神経のバランスを整えることで、夜間の過剰な便意を防ぐことが可能です。特に、ストレスが多い人や生活習慣が不規則な人は、自律神経が乱れやすく、それに伴い腸の働きも不安定になりがちです。
「夜になると必ずお腹が痛くなる」「寝ている途中で何度もトイレに行く」という症状が続く場合は、生活習慣の改善とともに、必要に応じて消化器内科の診察を受けることを検討することが大切です。
ストレスと腸の関係!緊張や不安で夜にトイレへ?
ストレスは、腸の働きに大きな影響を与える要因のひとつです。日常生活でストレスを感じていると、腸の動きが不規則になり、夜間に便意を催すことが増えることがあります。特に、仕事や家庭のプレッシャーが大きい人や、心配事が多い人ほど、夜間の腸の活動が過剰になる傾向があります。
ストレスが腸の働きに及ぼす影響
腸は「第二の脳」とも呼ばれるほど、自律神経の影響を強く受ける器官です。ストレスを感じると、交感神経が優位になり、腸の動きが抑制されます。しかし、ストレスが慢性化すると、その反動で腸が過剰に活動し、夜間に強い便意を引き起こすことがあります。
ストレスが腸に与える影響として、以下のような症状が見られます。
- 日中は便秘なのに、夜になると急に下痢になる
- 就寝前にお腹が張り、ゴロゴロと音がする
- 深夜に急な腹痛を感じ、トイレに駆け込む
これは、ストレスによって腸のぜん動運動が異常に亢進し、便が急激に移動するために起こる現象です。特に、過敏性腸症候群(IBS)を持つ人は、ストレスを受けると腸が過剰に反応し、夜間に下痢や便意が頻繁に起こることがあります。
ストレスを軽減し、夜間の腸の活動を抑える方法
夜間の便意を抑えるためには、ストレス管理が不可欠です。以下の方法を取り入れることで、腸の動きを安定させることができます。
①リラックスする時間を意識的に作る
日中のストレスをそのまま持ち越すと、夜間に腸の活動が活発になりやすくなります。就寝前にリラックスする時間を作り、ストレスを解消することが重要です。
- 温かいお風呂にゆっくり入る(38〜40℃のぬるめのお湯が効果的)
- 好きな音楽を聴く(自然音やクラシック音楽が自律神経を整える)
②腹式呼吸を行う
深い呼吸は、副交感神経を刺激し、腸の過剰な動きを抑える効果があります。特に、寝る前に腹式呼吸を行うことで、腸が落ち着き、夜間の便意を防ぐことができます。
- 鼻からゆっくり息を吸い、5秒間キープする
- 口からゆっくり息を吐きながら、お腹をへこませる。これを5分間繰り返す
③夜に必要以上に考え事をしないようにする
ストレスが強い人ほど、夜に過去の出来事を思い返したり、翌日のことを考えてしまう傾向があります。考えすぎると交感神経が活発になり、腸の活動が乱れる原因になります。
- 寝る前にスマホを見ない(ブルーライトが脳を活性化する)
- 1日の終わりに「今日良かったこと」を3つ書き出す(ポジティブな気持ちに切り替える)
- ストレスをコントロールすることで、腸の働きを安定させ、夜間の便意を抑えることができるのです。
ご予約はこちらから
当院では、夜間のトイレにお悩みの方にもしっかりと診察と検査を行います。場合によっては、内視鏡検査のご提案もいたします。まずは、外来のご予約のうえご来院ください。内視鏡検査を希望の場合には事前診察外来(大腸カメラの事前の相談・説明外来)、当日大腸カメラ(1日で診察から検査まで対応)でのWeb予約も可能です。24時間web予約が可能です。