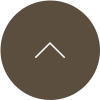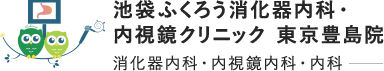便秘が引き起こす思わぬリスクと大腸がんとの関係



院長 柏木 宏幸所属学会・資格
- 日本内科学会 総合内科専門医
- 日本内科学会 内科認定医
- 日本消化器病学会 消化器病専門医
- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
- 一般社団法人日本病院総合診療医学会
認定病院総合診療医 - 難病指定医
- がん診療に関わる医師に対する緩和ケア 研修会 修了
- PEG・在宅医療研究会 修了証
便秘は「ただの不快な症状」と思われがちですが、放置するとさまざまな健康リスクを引き起こす可能性があります。特に近年の研究では、慢性的な便秘が大腸がんの発症リスクを高めることが指摘されています。なぜ便秘が大腸がんと関連するのか?そのメカニズムやリスク要因、予防策について詳しく解説していきます。
便秘とは?その定義と種類
①便秘の定義
便秘とは、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)が低下し、スムーズに排便できない状態を指します。便の回数が少ないだけでなく、排便の際に強くいきむ必要がある、残便感がある、硬い便が出るといった症状も便秘の一種です。
②便秘の種類
便秘には以下のような種類があります。
- ・機能性便秘:食生活やストレス、運動不足などが原因で起こる便秘。
- ・器質性便秘:腸の病気(狭窄、腸閉塞、がんなど)による便秘。
- ・薬剤性便秘:薬の副作用で腸の動きが鈍くなることによる便秘。
- ・習慣性便秘:便意を我慢する習慣が原因で起こる便秘。
慢性的な便秘を放置すると、腸内環境が悪化し、大腸がんのリスクを高める要因となります。
便秘が引き起こす健康リスクとは?
便秘は単に排便が困難になるだけの症状ではなく、全身の健康に影響を及ぼすことが分かっています。特に長期間にわたる慢性的な便秘は、消化器系だけでなく、皮膚、免疫系、精神状態にも悪影響を与える可能性があります。
便秘による悪玉菌の増加
便秘が続くと、腸内に便が長くとどまり、その間に悪玉菌が増殖します。これにより、有害なガスや毒素が発生し、それらが腸壁を通じて血液中に取り込まれることで、肌荒れや体臭、免疫力の低下などを引き起こすと考えられています。また、便秘による腸内環境の悪化は、セロトニン(幸せホルモン)の分泌を減少させ、気分の落ち込みや不安を引き起こすこともあります。
便秘による血流の悪化や自律神経の乱れ
便秘の影響は腸内にとどまらず、血流の悪化や自律神経の乱れにもつながります。腸の動きが鈍くなることで、腸壁の血流が滞り、腸の粘膜がダメージを受けやすくなります。この状態が続くと、慢性的な炎症を引き起こし、それが最終的に大腸がんの発症リスクを高める原因となるのです。便秘が続いている人は、早めに生活習慣を見直し、腸内環境の改善に努めることが重要です。
腸内環境の悪化と発がんリスクの増加
 便秘が長引くと、腸内の環境は大きく乱れます。腸には善玉菌、悪玉菌、そして日和見菌と呼ばれる細菌が存在し、通常はこれらがバランスを保ちながら共存しています。しかし、便秘によって排便の回数が減ると、腸内に老廃物が溜まり、悪玉菌が増殖しやすくなります。その結果、腸内の発酵・腐敗が進み、有害な物質が発生しやすくなります。
便秘が長引くと、腸内の環境は大きく乱れます。腸には善玉菌、悪玉菌、そして日和見菌と呼ばれる細菌が存在し、通常はこれらがバランスを保ちながら共存しています。しかし、便秘によって排便の回数が減ると、腸内に老廃物が溜まり、悪玉菌が増殖しやすくなります。その結果、腸内の発酵・腐敗が進み、有害な物質が発生しやすくなります。
悪玉菌の増加による慢性的な炎症
悪玉菌が増えると、腸内でアンモニアや硫化水素、フェノールといった有害物質が生成され、これらが腸の粘膜を刺激することで、慢性的な炎症が引き起こされます。こうした炎症が続くと、腸の細胞がダメージを受け、異常増殖するリスクが高まります。つまり、長期間便秘を放置することは、腸の慢性炎症を引き起こし、がん細胞の発生を促す環境を作ってしまう可能性があるのです。
悪玉菌の増加による免疫機能の低下
悪玉菌の増加により、腸内の免疫機能が低下することも問題です。腸は体内の免疫システムの約70%を担っているといわれていますが、腸内環境が悪化すると、この免疫機能が正常に働かなくなり、がん細胞が発生しても排除しにくくなるのです。このように、便秘による腸内環境の悪化は、単なる不快な症状にとどまらず、大腸がんを含むさまざまな疾患のリスクを高める要因となるため、早めの対策が必要です。
便秘が続くと腸内で何が起こるのか?
 便秘が続くと、腸内ではさまざまな悪影響が生じます。通常、腸は蠕動運動(ぜんどううんどう)と呼ばれる動きをすることで、消化物をスムーズに移動させ、排便を促します。しかし、便秘になると蠕動運動が低下し、便が長時間腸内に滞留することになります。すると、便の水分がどんどん吸収されて硬くなり、ますます排便しづらい状態になります。
便秘が続くと、腸内ではさまざまな悪影響が生じます。通常、腸は蠕動運動(ぜんどううんどう)と呼ばれる動きをすることで、消化物をスムーズに移動させ、排便を促します。しかし、便秘になると蠕動運動が低下し、便が長時間腸内に滞留することになります。すると、便の水分がどんどん吸収されて硬くなり、ますます排便しづらい状態になります。
さらに、便が腸内に長く留まることで、悪玉菌が増殖しやすくなり、腸内の腐敗が進行します。腐敗によって発生するアンモニアやインドール、スカトールといった毒素は、腸壁を刺激し、慢性的な炎症を引き起こす要因になります。こうした炎症が長引くと、腸粘膜の細胞が傷つき、修復と増殖を繰り返すうちに異常な細胞が発生しやすくなります。これが、がん細胞の形成につながるのです。
また、便秘の影響は腸内だけにとどまりません。便秘がひどくなると、腸内の圧力が上昇し、血流が悪化します。これにより、腸だけでなく全身の代謝が低下し、免疫力の低下や肌荒れ、頭痛といった症状を引き起こすこともあります。便秘を単なる一時的な不調と考えず、早めに対策を講じることが、健康を維持するためには不可欠です。
慢性的な便秘と大腸がん発症のメカニズム
 慢性的な便秘は、大腸がんの発症リスクを高めるといわれています。その主なメカニズムとしては、腸内に滞留する便が発がん性物質を生み出し、それが腸粘膜に長期間接触することで細胞の異常増殖を引き起こす点が挙げられます。
慢性的な便秘は、大腸がんの発症リスクを高めるといわれています。その主なメカニズムとしては、腸内に滞留する便が発がん性物質を生み出し、それが腸粘膜に長期間接触することで細胞の異常増殖を引き起こす点が挙げられます。
腸内環境の悪化
便秘が続くと、腸内環境が悪化し、善玉菌の数が減少する一方で、悪玉菌が増加します。悪玉菌は腸内でタンパク質を分解する際にアミン類やニトロソアミンといった発がん性物質を生成します。これらの物質が腸の粘膜を刺激し続けることで、腸の細胞がダメージを受け、炎症を繰り返すようになります。この慢性的な炎症が、大腸がんの発生を促進するのです。
酸素供給の低下
便秘が続くと腸の動きが鈍くなり、腸内の酸素供給が低下するため、がん細胞が生存しやすい環境が整ってしまいます。がん細胞は酸素の少ない環境を好むため、便秘によって腸内の酸素濃度が低下すると、がんの成長が促進される可能性があるのです。
大腸ポリープの発生率の増加
便秘が長期間続くと、大腸ポリープの発生率が高まることも知られています。大腸ポリープの中には、良性のものもありますが、長い時間をかけてがん化するものもあるため、定期的な検診と便秘の改善が重要です。
慢性的な便秘を放置すると、大腸がんの発症リスクが着実に高まるため、早めに適切な対策を取ることが健康を守る鍵となります。
便秘と腸内細菌の関係:善玉菌と悪玉菌のバランス
腸内には、約100兆個以上の腸内細菌が存在し、腸内環境を整える重要な役割を果たしています。これらの細菌は、主に善玉菌・悪玉菌・日和見菌の3つに分類され、それぞれが腸内の健康に影響を与えます。
腸内細菌のバランスが乱れる
便秘になると、腸内に便が長期間滞留するため、腸内の細菌バランスが崩れやすくなります。通常であれば、善玉菌が優勢な状態を維持し、腸の働きを活発に保っていますが、便秘が続くことで悪玉菌が増殖しやすくなります。悪玉菌が増えると、腸内で有害なガスや毒素が発生し、それが腸粘膜を刺激して炎症を引き起こす要因になります。
悪玉菌の増加
悪玉菌が優勢になると、腸内の発酵・腐敗が進み、発がん性物質(アンモニア、フェノール、インドールなど)が作られやすくなります。これらの物質が腸壁を傷つけ、細胞の変異を促進することで、大腸がんのリスクが高まると考えられています。
便秘を予防・解消するためには、腸内細菌のバランスを整えることが非常に重要です。発酵食品や食物繊維を積極的に摂取し、善玉菌を増やすことで、腸内環境を改善し、がんのリスクを軽減することができます。
腸内の炎症と発がんリスクの関連性
便秘が続くと、腸内の悪玉菌が増殖し、有害物質が作られやすくなります。これにより、腸の粘膜が慢性的な刺激を受け、炎症が発生しやすくなります。腸の炎症が長期化すると、腸粘膜の細胞がダメージを受け、細胞の修復と再生が頻繁に行われるようになります。この過程で、異常な細胞が増殖しやすくなり、がんの発生につながる可能性があるのです。
腸内の炎症
腸内の炎症は、免疫機能の低下にも影響を及ぼします。腸には、体内の免疫機能の約7割が集中しているといわれており、腸内環境が悪化すると、がん細胞を排除する能力も低下してしまいます。その結果、がん細胞が発生した場合に、体がそれを抑制することが難しくなるため、大腸がんの進行リスクが高まるのです。
このように、腸内の炎症を抑えることは、便秘の解消だけでなく、大腸がんの予防にも直結します。抗炎症作用のある食品を摂取したり、ストレスを適切に管理したりすることで、腸の健康を維持することが大切です。
運動不足と便秘、大腸がんの関係性
 運動不足は、便秘を悪化させる大きな要因のひとつです。体を動かさないと、腸の蠕動運動が低下し、便の排出が滞りやすくなります。特に、デスクワークが中心の生活を送っている人や、長時間座りっぱなしの習慣がある人は、便秘になりやすい傾向があります。
運動不足は、便秘を悪化させる大きな要因のひとつです。体を動かさないと、腸の蠕動運動が低下し、便の排出が滞りやすくなります。特に、デスクワークが中心の生活を送っている人や、長時間座りっぱなしの習慣がある人は、便秘になりやすい傾向があります。
運動不足は肥満の原因ともなり、これが大腸がんのリスクを高める要因にもなります。肥満になると、体内の炎症反応が強まり、腸内の免疫機能が低下することで、がん細胞が増殖しやすい環境が整ってしまうのです。
適度な運動を習慣化することで、腸の動きを活発にし、便秘を解消することができます。ウォーキングやストレッチ、ヨガなどの軽い運動でも効果があるため、日常生活に取り入れることをお勧め致します。
ストレスが腸に与える影響とがんリスク
ストレスは、腸の働きを大きく左右する要因のひとつです。過度なストレスがかかると、自律神経のバランスが崩れ、腸の動きが鈍くなります。これにより、便秘が慢性化し、腸内環境が悪化することで、大腸がんのリスクが高まる可能性があります。
ストレスが腸の働きに及ぼす影響
ストレスを受けると、交感神経が優位になり、腸の蠕動運動が抑制されるため、便がスムーズに排出されにくくなります。また、ストレスが続くと腸内の善玉菌が減少し、悪玉菌が増殖しやすくなるため、炎症が発生しやすくなります。このような状態が続くと、腸の健康が損なわれ、最終的にがんの発生につながることも考えられます。
ストレス管理のためには、適度な運動や趣味の時間を確保し、リラックスできる環境を整えることが重要です。
便秘を解消するための生活習慣の改善ポイント
 便秘を解消し、大腸がんのリスクを減らすためには、生活習慣の見直しが不可欠です。特に、食事・運動・ストレス管理・水分補給の4つのポイントを意識することで、腸内環境を整え、便秘を改善することができます。
便秘を解消し、大腸がんのリスクを減らすためには、生活習慣の見直しが不可欠です。特に、食事・運動・ストレス管理・水分補給の4つのポイントを意識することで、腸内環境を整え、便秘を改善することができます。
①食生活の改善
食生活では、食物繊維を豊富に含む食品を積極的に摂取することが重要です。食物繊維には、水溶性と不溶性の2種類があり、それぞれ異なる働きをします。水溶性食物繊維(海藻類、オートミール、バナナなど)は便を柔らかくし、スムーズな排便を促します。一方で、不溶性食物繊維(野菜、豆類、玄米など)は腸を刺激し、蠕動運動を活発にする効果があります。どちらの食物繊維もバランスよく摂取することで、腸内環境が改善されます。
②運動習慣の見直し
運動習慣を取り入れることも大切です。特に、ウォーキングやヨガ、軽いストレッチなどは、腸の動きを促進し、便秘を解消するのに効果的です。毎日30分程度の運動を継続することで、腸が活発に動き、自然な排便をサポートしてくれます。
③ストレス管理
ストレス管理も便秘解消には欠かせません。ストレスが溜まると、自律神経が乱れ、腸の動きが低下します。これを防ぐためには、リラックスできる時間を確保することが重要です。趣味の時間を持ったり、深呼吸や瞑想を取り入れたりすることで、ストレスを軽減し、腸の健康を守ることができます。
④水分補給
水分補給を意識することも忘れてはいけません。水分が不足すると便が硬くなり、排出しにくくなります。1日に1.5〜2リットルの水をこまめに摂取することで、腸内の水分量を増やし、便をスムーズに出しやすくなります。特に、朝起きた直後にコップ1杯の水を飲むことで、腸が刺激され、排便が促されるのでおすすめです。
このように、生活習慣を少しずつ改善することで、便秘の解消だけでなく、大腸がんの予防にもつながります。
大腸がん予防のための腸活とは?
近年、「腸活」という言葉が注目されています。腸活とは、腸内環境を整え、腸の働きを活発にすることで、健康を維持するための習慣のことを指します。便秘を解消し、大腸がんを予防するためには、腸活を意識した生活を送ることがとても重要です。
腸内フローラを整えること
腸活の基本は、「腸内フローラを整えること」です。腸内フローラとは、腸の中に住む細菌の集まりのことで、善玉菌・悪玉菌・日和見菌のバランスが整っていることが理想的です。このバランスを維持するためには、発酵食品(ヨーグルト、納豆、味噌、ぬか漬けなど)を積極的に摂取することが有効です。発酵食品に含まれる乳酸菌やビフィズス菌は、腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を改善する効果があります。
規則正しい生活
腸活には規則正しい生活リズムも欠かせません。特に、毎朝決まった時間にトイレに行く習慣をつけることが重要です。便意がなくてもトイレに座ることで、排便のリズムが整いやすくなります。
食生活の改善
腸内の温度を適切に保つことも腸活には大切です。冷たい飲み物や食べ物を摂りすぎると、腸の動きが鈍くなり、便秘を引き起こす原因となるため、常温または温かい飲み物を選ぶようにしましょう。
このように、腸活を意識した生活を送ることで、腸の働きを高め、便秘を解消し、大腸がんのリスクを減らすことができます。
定期的な健康診断と便秘改善の重要性
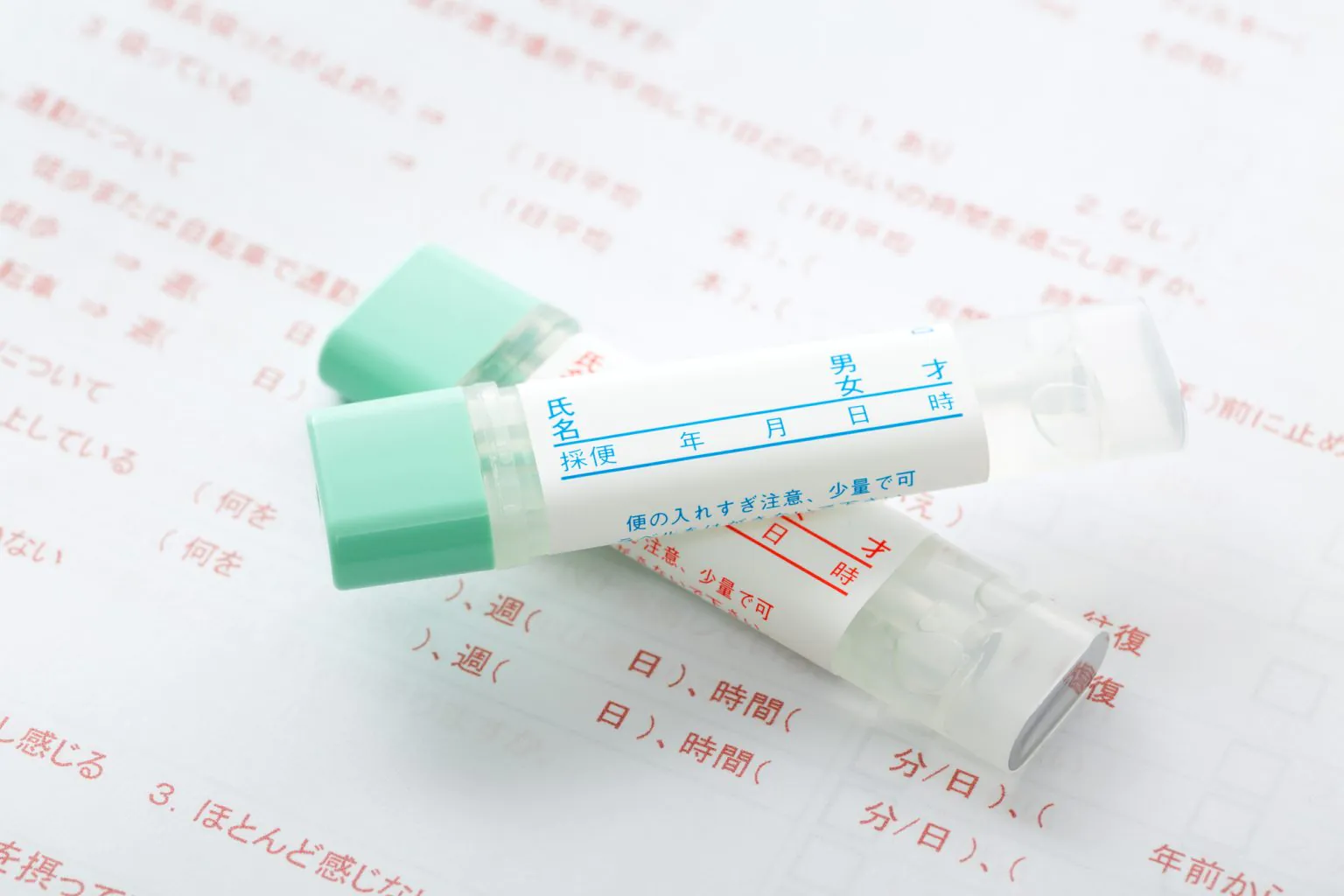 便秘が続いている場合、大腸がんのリスクを低減するためにも、定期的な健康診断を受けることが推奨されます。特に、40歳以上の人は、年に1回の大腸がん検診を受けることが望ましいとされています。
便秘が続いている場合、大腸がんのリスクを低減するためにも、定期的な健康診断を受けることが推奨されます。特に、40歳以上の人は、年に1回の大腸がん検診を受けることが望ましいとされています。
大腸がん
大腸がんは、早期発見・早期治療が可能な疾患のひとつです。初期の大腸がんは自覚症状がほとんどないため、便秘や血便、腹痛などの症状が現れたときには、すでに進行していることもあります。そのため、便秘が続いている場合は、「ただの便秘」と軽視せず、医療機関を受診することが重要です。
健康診断
健康診断では、便潜血検査や大腸内視鏡検査が大腸がんの早期発見に役立ちます。便潜血検査は、自宅で手軽に受けられる検査であり、便の中に血液が混じっているかを調べるものです。一方、大腸内視鏡検査は、腸内のポリープや炎症の有無を直接確認することができ、より正確な診断が可能です。また、健康診断を受けることで、自分の腸の状態を知ることができ、生活習慣の改善にもつなげることができます。便秘を長期間放置せず、定期的に検査を受けることで、大腸がんの予防と早期発見が可能になります。
ご予約はこちらから
当院では、便秘でお困りの方にもしっかりと診察と検査を行います。場合によっては、内視鏡検査のご提案もいたします。まずは、外来のご予約のうえご来院ください。24時間web予約が可能です。