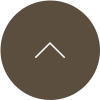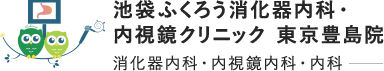「コーヒーを飲むとお腹がゴロゴロ…」カフェインと腸の関係を解説!



院長 柏木 宏幸所属学会・資格
- 日本内科学会 総合内科専門医
- 日本内科学会 内科認定医
- 日本消化器病学会 消化器病専門医
- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
- 一般社団法人日本病院総合診療医学会
認定病院総合診療医 - 難病指定医
- がん診療に関わる医師に対する緩和ケア 研修会 修了
- PEG・在宅医療研究会 修了証
コーヒーを飲むと「お腹がゴロゴロする」「急にトイレに行きたくなる」といった経験はありませんか?コーヒーを飲むと腸が活発になり、お腹が張ったり、下痢になったりする人がいます。これは、コーヒーに含まれるカフェインやその他の成分が腸の動きを刺激するためです。
特に、朝にコーヒーを飲んだ後に急にトイレに行きたくなる人は多いですが、これはカフェインが腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)を促進するためと考えられています。また、カフェイン以外にも、コーヒーに含まれる「クロロゲン酸」や「酸味成分」が胃腸に刺激を与えることが影響する場合もあります。
さらに、ミルクや砂糖を入れて飲む場合は、「乳糖不耐症(にゅうとうふたいしょう)」の影響でお腹が緩くなることもあります。つまり、コーヒーが腸に与える影響は人それぞれで、カフェインの作用、胃酸の分泌促進、乳糖の影響など、さまざまな要因が関係しているのです。
では、具体的にカフェインが腸にどのような影響を与えるのか、次の章で詳しく見ていきましょう。
カフェインが腸に与える影響とは?
コーヒーに含まれるカフェインは、脳を活性化させる覚醒作用があることで知られていますが、腸にも大きな影響を与えます。カフェインは腸の筋肉を刺激し、ぜん動運動を活発にすることで、便通を促す作用があります。
腹痛や下痢
 カフェインを摂取すると、自律神経の一種である交感神経が刺激され、腸の動きが活発になります。これは、腸の蠕動運動を助ける効果がある一方で、人によっては腸が過剰に反応し、腹痛や下痢を引き起こすことがあります。特に、過敏性腸症候群(IBS)を持つ人は、カフェインの刺激に敏感で、お腹が痛くなりやすい傾向があります。
カフェインを摂取すると、自律神経の一種である交感神経が刺激され、腸の動きが活発になります。これは、腸の蠕動運動を助ける効果がある一方で、人によっては腸が過剰に反応し、腹痛や下痢を引き起こすことがあります。特に、過敏性腸症候群(IBS)を持つ人は、カフェインの刺激に敏感で、お腹が痛くなりやすい傾向があります。
利尿作用
カフェインには利尿作用があり、体内の水分を排出しやすくするため、腸内の水分バランスが崩れ、便が柔らかくなりすぎたり、逆に腸が水分を吸収しすぎて便秘を引き起こしたりすることがあります。
カフェインは腸の動きを活発にし、便通を促す効果がある反面、過剰に摂取すると下痢や腹痛の原因になることもあるため、適量を意識することが重要です。
コーヒーの成分と腸の動きの関係
コーヒーが腸に影響を与えるのは、カフェインだけではありません。コーヒーにはさまざまな成分が含まれており、それらが腸の働きに影響を及ぼすことがあります。
①クロロゲン酸の影響
コーヒーには「クロロゲン酸」と呼ばれるポリフェノールの一種が含まれています。この成分は抗酸化作用があることで知られていますが、胃酸の分泌を促進する作用もあります。そのため、コーヒーを飲むと胃酸が多く分泌され、腸にも影響を与えることがあります。特に、空腹時にコーヒーを飲むと胃酸の影響が強くなり、腹痛や下痢の原因になることがあります。
②酸味成分の影響
コーヒーの種類によっては、酸味が強いものがあります。この酸味成分が腸を刺激し、腸の動きを活発にすることがあります。特に、胃酸の分泌が多い人は、酸味の強いコーヒーを飲むと胃腸に負担がかかりやすくなります。
③タンニンの影響
コーヒーには「タンニン」と呼ばれる成分も含まれています。タンニンはポリフェノールの一種で、抗酸化作用がありますが、鉄分の吸収を妨げる作用もあるため、貧血気味の人は注意が必要です。また、タンニンは腸の粘膜に作用し、便秘を引き起こすこともあります。
このように、カフェインだけでなく、クロロゲン酸や酸味成分、タンニンなどの影響で、コーヒーが腸の動きを変化させることがあるのです。
胃酸の分泌が腸に影響?コーヒーが胃腸に与える刺激とは
 コーヒーを飲むと胃酸の分泌が促進されることが知られています。これは、コーヒーに含まれる「カフェイン」や「クロロゲン酸」が胃の壁を刺激し、胃酸の分泌を活発にするためです。適度な胃酸分泌は食べ物の消化を助ける働きをしますが、過剰に分泌されると胃や腸に負担をかけ、腹痛や下痢の原因になることがあります。
コーヒーを飲むと胃酸の分泌が促進されることが知られています。これは、コーヒーに含まれる「カフェイン」や「クロロゲン酸」が胃の壁を刺激し、胃酸の分泌を活発にするためです。適度な胃酸分泌は食べ物の消化を助ける働きをしますが、過剰に分泌されると胃や腸に負担をかけ、腹痛や下痢の原因になることがあります。
胃もたれ・胸焼け・腹痛
空腹時にコーヒーを飲むと、食べ物がない状態で胃酸が分泌され、胃の粘膜を刺激します。その結果、胃もたれや胸焼け、さらには腸の過活動による腹痛が起こることがあります。また、胃酸が多く分泌されることで腸内のpHバランスが崩れ、腸の働きが不安定になる可能性もあります。
このような影響を避けるためには、空腹時にコーヒーを飲むのを控え、食後に摂取するのが望ましいです。また、胃が敏感な人は、酸味の強いコーヒーではなく、深煎りのマイルドなコーヒーを選ぶことで胃腸への負担を軽減できます。
乳糖不耐症の可能性も?カフェラテやカプチーノでお腹が緩くなる理由
 ブラックコーヒーではなく、カフェラテやカプチーノを飲むとお腹がゴロゴロする人は、乳糖不耐症(にゅうとうふたいしょう)の可能性があります。乳糖不耐症とは、牛乳に含まれる「乳糖(ラクトース)」を分解する酵素「ラクターゼ」の働きが弱いために、乳糖を十分に消化できず、腸内で発酵してガスや下痢を引き起こす症状のことです。
ブラックコーヒーではなく、カフェラテやカプチーノを飲むとお腹がゴロゴロする人は、乳糖不耐症(にゅうとうふたいしょう)の可能性があります。乳糖不耐症とは、牛乳に含まれる「乳糖(ラクトース)」を分解する酵素「ラクターゼ」の働きが弱いために、乳糖を十分に消化できず、腸内で発酵してガスや下痢を引き起こす症状のことです。
特に、日本人は乳糖を分解する酵素の活性が低い人が多く、牛乳を摂取するとお腹が緩くなる人が少なくありません。カフェラテやカプチーノには牛乳が多く含まれているため、乳糖不耐症の人が飲むと腸が刺激され、腹痛や下痢の原因になることがあります。もし、カフェラテを飲むとお腹が緩くなる場合は、牛乳の代わりに豆乳やアーモンドミルクを使用したカフェラテを選ぶと、腸への負担を軽減できる可能性があります。また、乳糖が分解された「低乳糖ミルク」を使うのも一つの方法です。
コーヒーと腸内細菌の関係!腸内環境に与える影響とは?
 コーヒーは腸内細菌のバランスにも影響を与えることが分かっています。腸内には善玉菌・悪玉菌・日和見菌がバランスよく存在していますが、コーヒーに含まれるポリフェノール(クロロゲン酸など)や食物繊維が善玉菌の増殖を助ける効果があるといわれています。
コーヒーは腸内細菌のバランスにも影響を与えることが分かっています。腸内には善玉菌・悪玉菌・日和見菌がバランスよく存在していますが、コーヒーに含まれるポリフェノール(クロロゲン酸など)や食物繊維が善玉菌の増殖を助ける効果があるといわれています。
カフェインの過剰摂取には注意を
コーヒーの飲みすぎやカフェインの過剰摂取は、腸のバランスを崩し、悪玉菌が増えやすい環境を作る可能性もあります。特に、カフェインが腸の動きを過剰に刺激すると、腸内のバランスが乱れ、下痢や便秘を繰り返しやすくなることがあります。
コーヒーを飲んで腸の調子が悪くなる場合は、一度コーヒーの摂取量を減らし、ヨーグルトや発酵食品などの腸内環境を整える食品を意識的に摂取することが大切です。
空腹時のコーヒーは危険?胃腸へのダメージと対策
朝起きてすぐにコーヒーを飲む習慣がある人は多いですが、空腹時のコーヒーは胃腸に負担をかける可能性があるため注意が必要です。
空腹時のコーヒーは胃痛や胸焼けの原因
コーヒーには、カフェインのほかに「クロロゲン酸」という成分が含まれています。これはポリフェノールの一種で抗酸化作用がありますが、胃酸の分泌を促進する働きもあるため、胃の粘膜を刺激しやすいのです。空腹時にコーヒーを飲むと、胃の中に食べ物がない状態で胃酸が分泌されるため、胃の粘膜に直接ダメージを与え、胃痛や胸焼けの原因となります。また、胃酸が過剰に分泌されると腸にも影響し、腹痛や下痢を引き起こすことがあります。
空腹時のコーヒーは便通異常の原因
カフェインには交感神経を刺激する作用があり、腸の動きが活発になりすぎることで、便が緩くなったり、腸が過剰に収縮して腹痛を感じたりすることがあります。特に、もともと胃腸が弱い人や、過敏性腸症候群(IBS)を持つ人は、空腹時のコーヒーが強い刺激となりやすい傾向があります。
このような影響を防ぐためには、コーヒーを飲む前に軽く食事を摂ることが重要です。例えば、バナナやヨーグルト、ナッツなどの消化に優しい食品を少量食べてからコーヒーを飲むと、胃酸の影響を和らげることができます。また、ミルクを加えたカフェオレやデカフェ(カフェインレス)コーヒーを選ぶことで、胃腸への刺激を抑えることができます。
コーヒーを飲むと下痢になる人と便秘になる人の違い
コーヒーを飲んだ後の腸の反応には個人差があり、ある人は下痢をしやすくなり、別の人は便秘になりやすくなるという違いがあります。この違いは、腸の性質や体質によるものです。
コーヒーを飲むと下痢になる人
 コーヒーを飲むと下痢になりやすい人は、カフェインやクロロゲン酸の刺激に敏感で、腸の蠕動運動が過剰に活発になりやすい傾向があります。カフェインは腸の筋肉を刺激し、便を押し出す動きを促進するため、腸が敏感な人はすぐに便意を感じ、下痢になりやすくなります。また、胃酸が過剰に分泌されることで腸内の環境が変化し、消化不良を引き起こすこともあります。
コーヒーを飲むと下痢になりやすい人は、カフェインやクロロゲン酸の刺激に敏感で、腸の蠕動運動が過剰に活発になりやすい傾向があります。カフェインは腸の筋肉を刺激し、便を押し出す動きを促進するため、腸が敏感な人はすぐに便意を感じ、下痢になりやすくなります。また、胃酸が過剰に分泌されることで腸内の環境が変化し、消化不良を引き起こすこともあります。
コーヒーを飲むと便秘になる人
 コーヒーを飲むと便秘になる人もいます。これは、カフェインの利尿作用によって体内の水分が排出されすぎるため、腸内の水分が不足し、便が硬くなりやすくなることが原因と考えられます。また、コーヒーに含まれるタンニンという成分には収れん作用(組織を引き締める作用)があり、腸の動きを抑制することがあるため、便秘になりやすい人もいるのです。
コーヒーを飲むと便秘になる人もいます。これは、カフェインの利尿作用によって体内の水分が排出されすぎるため、腸内の水分が不足し、便が硬くなりやすくなることが原因と考えられます。また、コーヒーに含まれるタンニンという成分には収れん作用(組織を引き締める作用)があり、腸の動きを抑制することがあるため、便秘になりやすい人もいるのです。
このように、コーヒーの影響は個人の腸の性質によって異なるため、自分の体質に合わせた飲み方を工夫することが重要です。例えば、コーヒーを飲む量を調整したり、カフェインの少ないデカフェを選んだりすることで、腸への影響をコントロールすることができます。
お腹に優しいコーヒーの選び方とは?
 コーヒーを飲むとお腹がゴロゴロしやすい人は、コーヒーの種類や淹れ方を工夫することで、腸への負担を軽減できる可能性があります。
コーヒーを飲むとお腹がゴロゴロしやすい人は、コーヒーの種類や淹れ方を工夫することで、腸への負担を軽減できる可能性があります。
デカフェ(カフェインレス)コーヒー
 カフェインの影響を受けやすい人は、デカフェ(カフェインレス)コーヒーを選ぶと良いでしょう。デカフェは通常のコーヒーよりもカフェインが少なく、胃腸への刺激が抑えられます。特に、夕方以降にコーヒーを飲みたい場合は、カフェインの影響を最小限に抑えられるデカフェが適しています。
カフェインの影響を受けやすい人は、デカフェ(カフェインレス)コーヒーを選ぶと良いでしょう。デカフェは通常のコーヒーよりもカフェインが少なく、胃腸への刺激が抑えられます。特に、夕方以降にコーヒーを飲みたい場合は、カフェインの影響を最小限に抑えられるデカフェが適しています。
深煎りのコーヒー
 コーヒーの酸味が強いと胃腸に負担がかかることがあるため、深煎りのコーヒーを選ぶのもおすすめです。深煎りのコーヒーは酸味が少なく、マイルドな味わいが特徴で、胃腸への刺激が少ないとされています。反対に、浅煎りのコーヒーは酸味が強く、胃酸の分泌を促しやすいため、胃が弱い人にはあまり向いていません。
コーヒーの酸味が強いと胃腸に負担がかかることがあるため、深煎りのコーヒーを選ぶのもおすすめです。深煎りのコーヒーは酸味が少なく、マイルドな味わいが特徴で、胃腸への刺激が少ないとされています。反対に、浅煎りのコーヒーは酸味が強く、胃酸の分泌を促しやすいため、胃が弱い人にはあまり向いていません。
コーヒーの淹れ方に工夫を
コーヒーの淹れ方にも工夫ができます。ペーパードリップで淹れたコーヒーは、油分が少なく、胃腸への負担が軽いといわれています。フレンチプレスやエスプレッソはコーヒーオイルが多く含まれており、人によっては胃腸に刺激を与える可能性があるため、腸が敏感な人はペーパードリップで淹れたコーヒーを試してみるのも良いでしょう。
コーヒーとストレスの関係!リラックス効果と腸の働き
コーヒーはリラックス効果があるといわれていますが、ストレスとの関係が腸の働きにも影響を与えることが分かっています。
カフェインの覚醒作用
カフェインには覚醒作用があり、脳を活性化させることで一時的に気分を高める効果があります。しかし、過剰に摂取すると交感神経が過度に刺激され、ストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌が増えます。この状態が続くと、自律神経のバランスが崩れ、腸の働きが不安定になり、便秘や下痢を引き起こしやすくなるのです。リラックスした状態では副交感神経が優位になり、腸の働きが正常に保たれます。しかし、コーヒーを飲むことで交感神経が刺激されると、腸の動きが過剰になったり、逆に抑制されたりすることがあります。特に、ストレスを感じやすい人や過敏性腸症候群(IBS)の人は、カフェインの影響を受けやすいため、コーヒーの量を調整することが大切です。
コーヒーを飲むとお腹がゴロゴロする原因
コーヒーを飲むとお腹がゴロゴロする原因には、カフェインの刺激、胃酸の分泌促進、乳糖不耐症、腸内環境の変化などが複雑に絡み合っていることが分かりました。しかし、コーヒーは適量を守れば健康に良い飲み物でもあります。腸への影響を抑えながらコーヒーを楽しむためには、以下のポイントに注意することが大切です。
- 空腹時にコーヒーを飲まない(軽く食事をしてから飲む)
- カフェインの摂取量をコントロールする(1日2〜3杯までが理想的)
- デカフェや深煎りコーヒーを選ぶ(胃腸への刺激を抑える)
- 牛乳の代わりに豆乳やアーモンドミルクを試す(乳糖不耐症の人向け)
- 水分補給をしっかり行う(カフェインの利尿作用による脱水を防ぐ)
このように、自分の体質に合った飲み方を見つけることで、コーヒーを楽しみながら腸の健康を保つことができます。無理のない範囲でコーヒーの量や種類を調整し、自分に合った飲み方を見つけていきましょう。
ご予約はこちらから
当院では消化器疾患、お腹のことでお困りの方にもしっかりと診察と検査を行います。場合によっては、内視鏡検査のご提案もいたします。まずは、外来のご予約のうえご来院ください。胃カメラ、大腸カメラを当日希望の方は胃カメラ、当日大腸カメラのWeb予約も可能です。24時間web予約が可能です。