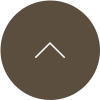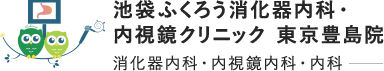女性が便秘に悩みやすい理由と根本解決に向けて



院長 柏木 宏幸所属学会・資格
- 日本内科学会 総合内科専門医
- 日本内科学会 内科認定医
- 日本消化器病学会 消化器病専門医
- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
- 一般社団法人日本病院総合診療医学会
認定病院総合診療医 - 難病指定医
- がん診療に関わる医師に対する緩和ケア 研修会 修了
- PEG・在宅医療研究会 修了証
「便秘がちでお腹がスッキリしない…」「長年、便秘に悩まされている」という女性は少なくありません。実際、便秘は男性よりも女性に多い症状であり、日本人女性の約2〜3割が慢性的な便秘を抱えていると言われています。では、なぜ女性は便秘になりやすいのでしょうか?その理由は、ホルモンバランス、筋力の違い、生活習慣、自律神経の影響など、さまざまな要因が関係しています。
本記事では、女性が便秘になりやすい理由を詳しく解説し、根本的な改善方法についても具体的に紹介します。便秘の悩みを解決し、腸の健康を取り戻すためのヒントを見つけていきましょう。
女性の便秘の特徴と男性との違い
発症率の違い
 便秘は男性と女性の両方に起こるものですが、発生率や症状の現れ方には大きな違いがあります。日本国内の調査では、女性の約2〜3割が慢性的な便秘を抱えているのに対し、男性の便秘の割合は比較的低いことが分かっています。この違いには、生理周期やホルモンバランス、筋力の違い、生活習慣などが関係しています。
便秘は男性と女性の両方に起こるものですが、発生率や症状の現れ方には大きな違いがあります。日本国内の調査では、女性の約2〜3割が慢性的な便秘を抱えているのに対し、男性の便秘の割合は比較的低いことが分かっています。この違いには、生理周期やホルモンバランス、筋力の違い、生活習慣などが関係しています。
男性と女性の便秘の主な違い
①便秘の発生率の違い
 男性よりも女性のほうが、便秘に悩む割合が高いことが知られています。これは、女性の腸が男性よりも長く、便が腸内にとどまりやすいためとも言われています。また、女性の腸は骨盤の形に沿って配置されているため、腸の動きが滞りやすいという特徴もあります。
男性よりも女性のほうが、便秘に悩む割合が高いことが知られています。これは、女性の腸が男性よりも長く、便が腸内にとどまりやすいためとも言われています。また、女性の腸は骨盤の形に沿って配置されているため、腸の動きが滞りやすいという特徴もあります。
②便秘のタイプの違い
 男性の場合、便秘はストレスや不規則な食生活が原因で起こることが多く、下痢と便秘を繰り返す過敏性腸症候群(IBS)に関連することがよくあります。一方で、女性の場合は、慢性的な便秘(排便回数が少ない)や、排便困難型の便秘が多いのが特徴です。
男性の場合、便秘はストレスや不規則な食生活が原因で起こることが多く、下痢と便秘を繰り返す過敏性腸症候群(IBS)に関連することがよくあります。一方で、女性の場合は、慢性的な便秘(排便回数が少ない)や、排便困難型の便秘が多いのが特徴です。
③便秘の原因の違い
 男性の便秘は、食生活の乱れや運動不足が主な原因ですが、女性はホルモンの影響や筋力の弱さ、ストレスの影響が大きいとされています。特に、生理前や妊娠中、更年期にかけて便秘が悪化しやすいのは、女性ホルモンが腸の動きを左右するためです。
男性の便秘は、食生活の乱れや運動不足が主な原因ですが、女性はホルモンの影響や筋力の弱さ、ストレスの影響が大きいとされています。特に、生理前や妊娠中、更年期にかけて便秘が悪化しやすいのは、女性ホルモンが腸の動きを左右するためです。
このように、女性の便秘は単なる生活習慣の問題ではなく、体の構造やホルモンバランスなどの生理的な要因が深く関わっているのです。
ホルモンバランスの影響と便秘の関係
 女性の便秘に大きな影響を与えているのが、ホルモンバランスの変化です。特に、生理周期に伴って変動するエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)が腸の動きに影響を与えます。
女性の便秘に大きな影響を与えているのが、ホルモンバランスの変化です。特に、生理周期に伴って変動するエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)が腸の動きに影響を与えます。
ホルモンと腸の働きの関係
①プロゲステロン(黄体ホルモン)が腸の動きを抑制
生理前に分泌が増加するプロゲステロンは、腸のぜん動運動を抑制する働きを持っています。これは、妊娠に備えて栄養を体内に長くとどめるための機能ですが、結果として腸の動きが鈍くなり、便秘が悪化しやすくなります。
②エストロゲンの減少が便の水分バランスを崩す
エストロゲンは、腸内で水分の吸収を調整する役割を持っています。しかし、生理前や閉経後にはエストロゲンの分泌量が減少し、腸の水分バランスが崩れることで、便が硬くなり、排便しにくくなることがあります。
③生理周期と便秘の関係
・生理前(黄体期) → プロゲステロンの影響で腸の動きが鈍くなり、便秘が悪化
・生理中 → 腸の活動が少しずつ回復するが、下痢になることも
・生理後(卵胞期) → エストロゲンの増加により、便秘が改善しやすい
このように、女性の便秘はホルモンの影響を大きく受けるため、生理周期を意識した食事や生活習慣の調整が必要になります。
筋力の違いが便秘を引き起こす?腹筋と腸の関係
 排便の際には、腸のぜん動運動だけでなく、腹筋や骨盤底筋の力が必要になります。しかし、女性は男性に比べて腹筋が弱いため、便を押し出す力が不足しやすいという特徴があります。
排便の際には、腸のぜん動運動だけでなく、腹筋や骨盤底筋の力が必要になります。しかし、女性は男性に比べて腹筋が弱いため、便を押し出す力が不足しやすいという特徴があります。
腹筋と便秘の関係
腸が便を送り出す動き(ぜん動運動)
 腸が便を送り出す動き(ぜん動運動)は、自律神経によってコントロールされていますが、最終的に便を排出するには腹圧(腹筋の力)が必要になります。女性は男性に比べて腹筋の量が少ないため、便を押し出す力が弱く、便秘になりやすいのです。特に運動不足が続くと、さらに腹筋が衰え、便秘が慢性化しやすくなります。
腸が便を送り出す動き(ぜん動運動)は、自律神経によってコントロールされていますが、最終的に便を排出するには腹圧(腹筋の力)が必要になります。女性は男性に比べて腹筋の量が少ないため、便を押し出す力が弱く、便秘になりやすいのです。特に運動不足が続くと、さらに腹筋が衰え、便秘が慢性化しやすくなります。
骨盤底筋の緩みが便秘を悪化させる
腸が便を送り出す動き(ぜん動運動)
 女性は妊娠・出産を経験すると、骨盤底筋が緩み、排便時にうまくいきめなくなることがあります。これにより、便秘が悪化しやすくなり、便秘薬に頼る頻度が増えることもあります。
女性は妊娠・出産を経験すると、骨盤底筋が緩み、排便時にうまくいきめなくなることがあります。これにより、便秘が悪化しやすくなり、便秘薬に頼る頻度が増えることもあります。
腹筋と便秘の関係
腸が便を送り出す動き(ぜん動運動)
 便秘の改善には、適度な腹筋トレーニングや、骨盤底筋を鍛えるエクササイズが効果的です。
便秘の改善には、適度な腹筋トレーニングや、骨盤底筋を鍛えるエクササイズが効果的です。
・腹筋運動(クランチ、レッグレイズ)を1日10回から始める
・骨盤底筋を鍛える「ドローイン」や「スクワット」を取り入れる
・日常生活で腹圧を意識し、姿勢を正しく保つ
筋力を鍛えることで、自然な排便がスムーズになり、便秘を根本から改善することができます。
女性に多い「我慢する習慣」が便秘を悪化させる理由
 女性は仕事や外出先で「トイレに行きにくい」「恥ずかしい」と感じ、便意を我慢することが多い傾向にあります。(もちろん個人差はあります。)しかし、便意を我慢することが習慣化すると、腸の反応が鈍くなり、便秘が慢性化しやすくなります。
女性は仕事や外出先で「トイレに行きにくい」「恥ずかしい」と感じ、便意を我慢することが多い傾向にあります。(もちろん個人差はあります。)しかし、便意を我慢することが習慣化すると、腸の反応が鈍くなり、便秘が慢性化しやすくなります。
便意を我慢するとどうなる?
・便が腸内に長時間とどまり、水分が過剰に吸収される → 硬くなり排出しにくくなる
・腸の神経が鈍感になり、便意を感じにくくなる → 便秘が慢性化
・腸内に便が停滞することで、悪玉菌が増加し腸内環境が悪化
便意を逃さないための習慣
・毎朝トイレに行く時間を確保する
・外出先でもトイレを我慢しない
・腸のリズムを整えるために、決まった時間にトイレに行く
便秘の改善には、「便意を逃さない習慣」を身につけることが大切です。最初は意識していかないといけないですが、徐々に習慣化していけるようにしていきましょう。
ストレスと自律神経の乱れが便秘を引き起こす仕組み
 ストレスは腸の働きに大きな影響を与える要因のひとつです。特に女性は、仕事や家庭のプレッシャー、人間関係の悩みなど、さまざまなストレスを抱えやすく、その影響で自律神経が乱れ、便秘になりやすくなります。
ストレスは腸の働きに大きな影響を与える要因のひとつです。特に女性は、仕事や家庭のプレッシャー、人間関係の悩みなど、さまざまなストレスを抱えやすく、その影響で自律神経が乱れ、便秘になりやすくなります。
交感神経と副交感神経
自律神経には、活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に働く「副交感神経」があり、この2つのバランスが腸の働きを調整しています。ストレスを感じると交感神経が活発になり、腸のぜん動運動が抑制されます。その結果、腸の動きが鈍くなり、便秘が悪化するのです。また、ストレスが長期間続くと、副交感神経がうまく機能せず、腸が慢性的に動きにくくなることもあります。これにより、便秘と下痢を交互に繰り返す「過敏性腸症候群(IBS)」を発症することも少なくありません。
ストレスのコントロール
 便秘を改善するには、ストレスを上手にコントロールし、自律神経のバランスを整えることが重要です。例えば、深呼吸やストレッチを行うことで副交感神経を活性化し、腸の動きを促進することができます。また、ぬるめのお風呂に入る、趣味の時間を作る、睡眠を十分にとるといった方法も、自律神経を整えるのに役立ちます。
便秘を改善するには、ストレスを上手にコントロールし、自律神経のバランスを整えることが重要です。例えば、深呼吸やストレッチを行うことで副交感神経を活性化し、腸の動きを促進することができます。また、ぬるめのお風呂に入る、趣味の時間を作る、睡眠を十分にとるといった方法も、自律神経を整えるのに役立ちます。
ストレスと腸の関係は密接であり、心と体の健康を両方ケアすることが、便秘の根本的な改善につながるのです。
食生活の乱れと食物繊維不足による便秘のリスク
女性の便秘の原因のひとつに、食生活の乱れが挙げられます。特に、忙しさから朝食を抜いたり、コンビニやファストフード中心の食生活を続けていると、腸の働きが低下し、便秘が慢性化しやすくなります。
食物繊維の摂取
 便秘改善に欠かせないのが、食物繊維の摂取です。食物繊維には、水に溶ける「水溶性食物繊維」と、水に溶けない「不溶性食物繊維」の2種類があり、どちらもバランスよく摂ることが重要です。水溶性食物繊維は、腸内の水分を保持し、便を柔らかくする働きがあります。これは、海藻類や果物、オートミールなどに多く含まれています。一方、不溶性食物繊維は、便のかさを増やし、腸を刺激して排便を促進します。これは、ごぼうや豆類、玄米などに豊富に含まれています。
便秘改善に欠かせないのが、食物繊維の摂取です。食物繊維には、水に溶ける「水溶性食物繊維」と、水に溶けない「不溶性食物繊維」の2種類があり、どちらもバランスよく摂ることが重要です。水溶性食物繊維は、腸内の水分を保持し、便を柔らかくする働きがあります。これは、海藻類や果物、オートミールなどに多く含まれています。一方、不溶性食物繊維は、便のかさを増やし、腸を刺激して排便を促進します。これは、ごぼうや豆類、玄米などに豊富に含まれています。
水分補給
 しかし、食物繊維を過剰に摂取すると、逆に便が硬くなり、腸内で詰まりやすくなることもあります。そのため、水溶性と不溶性のバランスを考えながら摂取することが大切です。また、食物繊維を摂る際には、十分な水分を一緒に摂ることで、腸内環境を整え、スムーズな排便を促すことができます。
しかし、食物繊維を過剰に摂取すると、逆に便が硬くなり、腸内で詰まりやすくなることもあります。そのため、水溶性と不溶性のバランスを考えながら摂取することが大切です。また、食物繊維を摂る際には、十分な水分を一緒に摂ることで、腸内環境を整え、スムーズな排便を促すことができます。
毎日の食事に意識的に食物繊維を取り入れることで、腸の健康を維持し、便秘の改善につながるのです。
水分不足が腸の動きを鈍らせる?水分摂取の重要性
便秘の原因として見落とされがちなのが、水分不足です。体の水分が不足すると、腸内の便が硬くなり、排出しにくくなります。特に女性は、男性に比べて水分摂取量が少ない傾向があり、それが慢性的な便秘の一因となっています
体内の水分バランス
腸は、体内の水分バランスを調整する役割も果たしています。体が脱水状態になると、腸はできるだけ水分を吸収しようとするため、便の水分量が減り、硬くなってしまうのです。その結果、便が腸内にとどまりやすくなり、便秘が悪化します。
利尿作用には注意を
 水分不足を防ぐためには、こまめな水分補給が大切です。朝起きたらコップ一杯の水を飲むことで、腸が刺激され、排便のスイッチが入ります。また、食事の際にも意識的に水分を摂ることで、便の水分量を増やし、スムーズな排便を促すことができます。特に、カフェインを多く含むコーヒーや紅茶、アルコールは利尿作用が強く、水分を排出しやすいため、飲みすぎには注意が必要です。水や白湯、ノンカフェインのお茶などを適度に摂取し、腸の働きをサポートすることが重要です。
水分不足を防ぐためには、こまめな水分補給が大切です。朝起きたらコップ一杯の水を飲むことで、腸が刺激され、排便のスイッチが入ります。また、食事の際にも意識的に水分を摂ることで、便の水分量を増やし、スムーズな排便を促すことができます。特に、カフェインを多く含むコーヒーや紅茶、アルコールは利尿作用が強く、水分を排出しやすいため、飲みすぎには注意が必要です。水や白湯、ノンカフェインのお茶などを適度に摂取し、腸の働きをサポートすることが重要です。
水分補給は、便秘解消のための基本的なケアのひとつであり、日々の習慣として取り入れることで、腸の調子を整えることができます。
運動不足が腸のぜん動運動を低下させる原因とは?
 腸の動きは、体を動かすことで刺激され、活発になります。しかし、デスクワークが多い人や運動習慣がない人は、腸のぜん動運動が低下し、便秘になりやすくなります。特に、女性は筋力が弱く、腹圧が低いため、運動不足が続くと腸の動きが鈍くなりやすい傾向があります。
腸の動きは、体を動かすことで刺激され、活発になります。しかし、デスクワークが多い人や運動習慣がない人は、腸のぜん動運動が低下し、便秘になりやすくなります。特に、女性は筋力が弱く、腹圧が低いため、運動不足が続くと腸の動きが鈍くなりやすい傾向があります。
適度な運動
 腸の動きを促すには、適度な運動を取り入れることが重要です。ウォーキングは手軽にできる運動のひとつで、腸の動きを刺激し、自然な排便を促す効果があります。また、ヨガやストレッチは、腹部をほぐし、腸の緊張を和らげることで、排便をスムーズにするのに役立ちます。
腸の動きを促すには、適度な運動を取り入れることが重要です。ウォーキングは手軽にできる運動のひとつで、腸の動きを刺激し、自然な排便を促す効果があります。また、ヨガやストレッチは、腹部をほぐし、腸の緊張を和らげることで、排便をスムーズにするのに役立ちます。
運動不足が続くと、腸の働きだけでなく、血流も悪くなり、腸内環境が悪化することもあります。毎日の生活の中で、少しずつ体を動かす習慣をつけることで、腸の働きを整え、便秘の解消につなげることができます。
便秘薬の使いすぎに注意!依存によるリスクと対策
便秘に悩む女性の中には、便秘薬(下剤)に頼る人も少なくありません。便秘薬は即効性があり、一時的に症状を改善するのに役立ちますが、長期間の使用は腸の機能を低下させ、薬なしでは排便できない状態になる危険性があります。
便秘薬

便秘薬にはいくつかの種類がありますが、特に刺激性下剤(センナ、ビサコジルなど)は腸を強制的に刺激し、排便を促すため、常用すると腸が自力で動く力を失い、依存症につながることがあります。これにより、「下剤を飲まないと排便できない」「服用量が増えていく」といった悪循環が生じるのです。また、便秘薬の乱用は、腸の粘膜を傷つけ、長期的には大腸の黒ずみ(大腸メラノーシス)を引き起こす可能性があります。さらに、電解質のバランスが崩れ、脱水症状やカリウム不足による筋力低下が起こることもあります。
食生活の見直し

便秘薬を使わずに腸の働きを整えるためには、まずは食生活の見直しが必要です。食物繊維を多く含む食品を摂取し、水分補給をこまめに行うことで、自然な排便を促すことができます。また、腸の動きを活発にするために、軽い運動や腸マッサージを取り入れるのも有効です。
便秘薬は「どうしても排便がないときの最終手段」として考え、基本的には腸の力を鍛え、自然な排便リズムを作ることを目指すのが理想です。
腸内フローラのバランスが崩れると便秘が悪化する?
 腸の健康を保つために重要なのが、腸内フローラ(腸内細菌叢)のバランスです。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が存在し、これらがバランスを取ることで腸の機能が正常に働きます。しかし、ストレスや食生活の乱れが続くと、悪玉菌が増え、腸内環境が悪化し、便秘になりやすくなるのです。
腸の健康を保つために重要なのが、腸内フローラ(腸内細菌叢)のバランスです。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が存在し、これらがバランスを取ることで腸の機能が正常に働きます。しかし、ストレスや食生活の乱れが続くと、悪玉菌が増え、腸内環境が悪化し、便秘になりやすくなるのです。
善玉菌

善玉菌は、腸の動きを活発にし、便を柔らかくする働きを持っています。ヨーグルトや納豆、味噌、ぬか漬けなどの発酵食品には善玉菌が豊富に含まれており、これらを摂取することで腸内環境を改善することができます。
悪玉菌

一方で、肉類や加工食品ばかり食べていると、悪玉菌が優勢になり、腸の働きが鈍くなります。また、食物繊維が不足すると、腸内の善玉菌のエサがなくなり、腸内フローラのバランスが崩れやすくなります。そのため、野菜や果物、豆類などの食物繊維を意識的に摂ることが重要です。
腸内フローラのバランスが整うと、腸のぜん動運動が活発になり、自然な排便が促されます。腸内環境を良好に保つためには、日々の食生活を見直し、善玉菌を増やす食品を積極的に摂る習慣をつけることが大切です。
生理周期と便秘の関係!月経前後の腸の動きを調整する方法
女性の便秘は、生理周期と密接に関係しています。特に生理前に便秘がひどくなるという人は少なくありません。これは、ホルモンの変化が腸の働きに影響を与えるためです。
生理周期と便秘
生理前(黄体期)

生理前(黄体期)になると、プロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌が増加します。このホルモンは、妊娠に備えて体に水分を保持する働きがあるため、腸の水分量が減少し、便が硬くなりやすくなります。また、腸のぜん動運動も抑制されるため、排便がスムーズに行われなくなります。
生理期間

生理が始まると、プロゲステロンの分泌が減少し、逆にエストロゲン(卵胞ホルモン)が増加します。このホルモンは腸の働きを活発にするため、生理中は便秘が解消しやすくなることが多いのです。
生理前における便秘予防

生理前の便秘を予防するためには、食生活の工夫が重要です。特に、生理前は水分を多めに摂取し、便の硬化を防ぐことが大切です。また、マグネシウムを多く含む食品(ナッツ類、バナナ、海藻など)を摂ると、腸の動きをサポートし、スムーズな排便が期待できます。
生理周期に合わせた腸のケアを意識することで、ホルモンの変化による便秘の影響を最小限に抑えることができます。
根本解決のための食事改善
便秘を根本から解決するためには、日々の食事を見直すことが不可欠です。特に、腸の働きを正常に保つために、腸に良い食べ物を意識的に取り入れることが重要になります。
便秘解消につながる食事
発酵食品

便秘改善に役立つ食品として、まず挙げられるのが発酵食品です。ヨーグルトや納豆、キムチ、味噌などの発酵食品には、腸内の善玉菌を増やし、腸の環境を整える働きがあります。これらを日常的に摂ることで、腸の働きを活発にし、自然な排便を促すことができます。
食物繊維

また、食物繊維の摂取も重要です。水溶性食物繊維は便を柔らかくし、不溶性食物繊維は腸を刺激して排便を促します。どちらか一方ではなく、両方をバランスよく摂ることが便秘改善には欠かせません。特に、果物、野菜、豆類、全粒穀物などを意識的に摂取することで、腸の働きをサポートできます。
規則正しい食生活
さらに、腸の働きを整えるためには、食事の時間や回数も重要です。不規則な食生活を続けていると、腸のリズムが乱れ、便秘が悪化しやすくなります。毎日決まった時間に食事を摂ることで、腸の動きを安定させることができます。
食生活の改善は、便秘解消のための基本であり、長期的な視点で続けることが大切です。
ご予約はこちらから
当院では、女性の便秘でお悩みの方にもしっかりと診察と検査を行います。場合によっては、内視鏡検査のご提案もいたします。まずは、外来のご予約のうえご来院ください。24時間web予約が可能です。