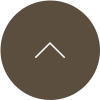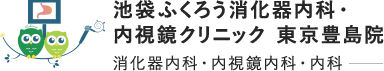下痢や腹痛が続く場合に疑われる重大な病気



院長 柏木 宏幸所属学会・資格
- 日本内科学会 総合内科専門医
- 日本内科学会 内科認定医
- 日本消化器病学会 消化器病専門医
- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
- 一般社団法人日本病院総合診療医学会
認定病院総合診療医 - 難病指定医
- がん診療に関わる医師に対する緩和ケア 研修会 修了
- PEG・在宅医療研究会 修了証
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 潰瘍性大腸炎
- クローン病
- 大腸がん
- 食中毒(細菌・ウイルス感染)
- 乳糖不耐症(ラクターゼ欠乏症)
- 下痢や腹痛が続くとはどういう状態なのか?正常な状態との違い
- 慢性的な下痢や腹痛の原因として考えられる生活習慣と環境要因
- 病院を受診するべきタイミングと適切な診断方法
- ご予約はこちらから
下痢や腹痛が続くと、多くの人は「一時的な体調不良だろう」と考えてしまいがちですが、実は深刻な病気のサインである可能性があります。特に、一週間以上続く下痢や、血便を伴う腹痛、体重減少、発熱などが見られる場合は、速やかに医療機関を受診する必要があります。ここでは、下痢や腹痛が続く場合に疑われる重大な病気について詳しく解説します。
過敏性腸症候群(IBS)
過敏性腸症候群(IBS)
 過敏性腸症候群(IBS)は、腸に器質的な異常が見られないにもかかわらず、慢性的な腹痛や下痢、便秘を繰り返す病気です。発症の原因としては、ストレスや不規則な生活習慣、腸内環境の乱れなどが関与していると考えられています。IBSの特徴としては、症状が長期間続くものの、腸に炎症や潰瘍などの明確な病変が見られない点が挙げられます。多くの患者は、仕事や学校などのプレッシャーを感じる場面で症状が悪化し、リラックスすると改善する傾向があります。そのため、ストレスマネジメントが治療の鍵となります。
過敏性腸症候群(IBS)は、腸に器質的な異常が見られないにもかかわらず、慢性的な腹痛や下痢、便秘を繰り返す病気です。発症の原因としては、ストレスや不規則な生活習慣、腸内環境の乱れなどが関与していると考えられています。IBSの特徴としては、症状が長期間続くものの、腸に炎症や潰瘍などの明確な病変が見られない点が挙げられます。多くの患者は、仕事や学校などのプレッシャーを感じる場面で症状が悪化し、リラックスすると改善する傾向があります。そのため、ストレスマネジメントが治療の鍵となります。
過敏性腸症候群(IBS)の種類
 また、IBSは大きく「下痢型」「便秘型」「混合型」の3種類に分類されます。下痢型では食後すぐに腹痛とともに下痢が起こり、特に朝や緊張した場面で症状が悪化します。一方、便秘型は腹痛を伴いながらも便秘が続き、排便後もすっきりしない感じが残ります。混合型では下痢と便秘を繰り返すのが特徴です。治療には、食事の改善、ストレス管理、運動習慣の見直しなどが必要ですが、症状が重い場合には医師の指導のもと薬物療法を行うこともあります。
また、IBSは大きく「下痢型」「便秘型」「混合型」の3種類に分類されます。下痢型では食後すぐに腹痛とともに下痢が起こり、特に朝や緊張した場面で症状が悪化します。一方、便秘型は腹痛を伴いながらも便秘が続き、排便後もすっきりしない感じが残ります。混合型では下痢と便秘を繰り返すのが特徴です。治療には、食事の改善、ストレス管理、運動習慣の見直しなどが必要ですが、症状が重い場合には医師の指導のもと薬物療法を行うこともあります。
潰瘍性大腸炎
 潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に炎症が起こり、びらんや潰瘍が形成される病気です。主な症状として、粘血便(血液や粘液を含む便)、下痢、腹痛、発熱、体重減少などが挙げられます。この病気は自己免疫疾患の一つとされ、免疫系が誤って腸の粘膜を攻撃することで炎症が引き起こされると考えられています。特に20代から30代の若年層に発症することが多く、日本でも患者数が増加傾向にあります。
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に炎症が起こり、びらんや潰瘍が形成される病気です。主な症状として、粘血便(血液や粘液を含む便)、下痢、腹痛、発熱、体重減少などが挙げられます。この病気は自己免疫疾患の一つとされ、免疫系が誤って腸の粘膜を攻撃することで炎症が引き起こされると考えられています。特に20代から30代の若年層に発症することが多く、日本でも患者数が増加傾向にあります。
潰瘍性大腸炎の種類
潰瘍性大腸炎には、「全大腸炎型」「左側大腸炎型」「直腸炎型」などの種類があり、炎症の広がりによって症状の程度が異なります。症状は「寛解期(落ち着いている状態)」と「活動期(症状が悪化する状態)」を繰り返すため、長期的な管理が必要です。治療には、5-アミノサリチル酸製剤(5-ASA)、ステロイド、免疫抑制剤などが用いられますが、重症化すると外科手術が必要になることもあります。生物学的製剤やJAK阻害薬といった新しい治療法が増えており、病状を安定させるための選択肢が増えています。
クローン病
 クローン病は、口から肛門までの消化管全体に炎症を引き起こす慢性疾患です。特に小腸と大腸に炎症が起こることが多く、下痢、腹痛、体重減少、発熱などの症状が見られます。原因はまだ完全には解明されていませんが、遺伝的要因や免疫系の異常、腸内細菌の関与が考えられています。クローン病は若年層(10代から30代)に多く発症し、一度発症すると完治することは難しく、生涯にわたって管理が必要な病気です。
クローン病は、口から肛門までの消化管全体に炎症を引き起こす慢性疾患です。特に小腸と大腸に炎症が起こることが多く、下痢、腹痛、体重減少、発熱などの症状が見られます。原因はまだ完全には解明されていませんが、遺伝的要因や免疫系の異常、腸内細菌の関与が考えられています。クローン病は若年層(10代から30代)に多く発症し、一度発症すると完治することは難しく、生涯にわたって管理が必要な病気です。
クローン病の特徴
 クローン病の特徴は、腸管の様々な部位に炎症が生じる「非連続性の病変」です。炎症が進行すると腸管が狭窄し、食事をすると激しい腹痛が生じることがあります。また、長期間の炎症によって腸に穴が開く「瘻孔(ろうこう)」や、腸と腸がくっついてしまう「癒着」が起こることもあります。クローン病は食生活と深く関係しており、高脂肪食や加工食品の摂取が多いと症状が悪化することが知られています。そのため、低脂肪・低残渣(ていざんさ)食を心がけ、腸に負担をかけない食事をすることが重要です。
クローン病の特徴は、腸管の様々な部位に炎症が生じる「非連続性の病変」です。炎症が進行すると腸管が狭窄し、食事をすると激しい腹痛が生じることがあります。また、長期間の炎症によって腸に穴が開く「瘻孔(ろうこう)」や、腸と腸がくっついてしまう「癒着」が起こることもあります。クローン病は食生活と深く関係しており、高脂肪食や加工食品の摂取が多いと症状が悪化することが知られています。そのため、低脂肪・低残渣(ていざんさ)食を心がけ、腸に負担をかけない食事をすることが重要です。
クローン病の治療
 治療には、抗炎症薬、免疫抑制剤、生物学的製剤などが用いられますが、病状が進行すると手術が必要になることもあります。しかし、手術を行っても再発することが多いため、できるだけ薬物療法で病状をコントロールしながら生活することが推奨されています。クローン病は適切な治療と生活管理を行うことで、症状をコントロールしながら日常生活を送ることが可能ですが、定期的な診察と検査が欠かせません。
治療には、抗炎症薬、免疫抑制剤、生物学的製剤などが用いられますが、病状が進行すると手術が必要になることもあります。しかし、手術を行っても再発することが多いため、できるだけ薬物療法で病状をコントロールしながら生活することが推奨されています。クローン病は適切な治療と生活管理を行うことで、症状をコントロールしながら日常生活を送ることが可能ですが、定期的な診察と検査が欠かせません。
大腸がん
 大腸がんは、日本において罹患率が高いがんの一つであり、特に40歳以上の人に多く見られます。初期段階ではほとんど自覚症状がないため、気づかずに進行してしまうことが多いですが、症状が現れ始めると、下痢や便秘を繰り返す、血便が出る、腹痛が続く、体重が減少するといった特徴が見られます。がんが進行すると、腸が狭くなり、排便が困難になることもあります。大腸がんは、早期に発見できれば治療の成功率が高い病気ですが、発見が遅れると治療が難しくなり、転移のリスクも高まります。
大腸がんは、日本において罹患率が高いがんの一つであり、特に40歳以上の人に多く見られます。初期段階ではほとんど自覚症状がないため、気づかずに進行してしまうことが多いですが、症状が現れ始めると、下痢や便秘を繰り返す、血便が出る、腹痛が続く、体重が減少するといった特徴が見られます。がんが進行すると、腸が狭くなり、排便が困難になることもあります。大腸がんは、早期に発見できれば治療の成功率が高い病気ですが、発見が遅れると治療が難しくなり、転移のリスクも高まります。
大腸がんの原因
 大腸がんの原因としては、食生活の欧米化が関係していると言われています。特に高脂肪・高たんぱく質の食事を摂ることが多い人、食物繊維の摂取が少ない人は、大腸がんのリスクが高くなります。また、家族に大腸がんの既往歴がある場合、遺伝的な要因も考えられます。さらに、慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)を患っている人も、大腸がんのリスクが高くなるため注意が必要です。
大腸がんの原因としては、食生活の欧米化が関係していると言われています。特に高脂肪・高たんぱく質の食事を摂ることが多い人、食物繊維の摂取が少ない人は、大腸がんのリスクが高くなります。また、家族に大腸がんの既往歴がある場合、遺伝的な要因も考えられます。さらに、慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)を患っている人も、大腸がんのリスクが高くなるため注意が必要です。
大腸がんの診断
 大腸がんの診断には、大腸内視鏡検査や便潜血検査が用いられます。特に、40歳以上の人や、家族歴がある人は、定期的な検査を受けることが推奨されています。治療法としては、手術によるがんの切除が一般的ですが、がんが進行している場合には、化学療法や放射線療法が併用されることもあります。早期発見・早期治療が鍵となるため、下痢や便秘が長期間続いたり、血便が見られる場合は、すぐに医療機関を受診することが大切です。
大腸がんの診断には、大腸内視鏡検査や便潜血検査が用いられます。特に、40歳以上の人や、家族歴がある人は、定期的な検査を受けることが推奨されています。治療法としては、手術によるがんの切除が一般的ですが、がんが進行している場合には、化学療法や放射線療法が併用されることもあります。早期発見・早期治療が鍵となるため、下痢や便秘が長期間続いたり、血便が見られる場合は、すぐに医療機関を受診することが大切です。
食中毒(細菌・ウイルス感染)
 食中毒は、細菌やウイルスが付着した食品を摂取することで発症する疾患であり、特に夏場や湿気の多い時期に多く発生します。原因となる細菌としては、サルモネラ菌、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌(O-157)などがあり、ウイルスとしてはノロウイルスやロタウイルスが代表的です。これらの病原体が腸内で増殖すると、激しい下痢、腹痛、嘔吐、発熱などの症状を引き起こします。
食中毒は、細菌やウイルスが付着した食品を摂取することで発症する疾患であり、特に夏場や湿気の多い時期に多く発生します。原因となる細菌としては、サルモネラ菌、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌(O-157)などがあり、ウイルスとしてはノロウイルスやロタウイルスが代表的です。これらの病原体が腸内で増殖すると、激しい下痢、腹痛、嘔吐、発熱などの症状を引き起こします。
食中毒の症状
食中毒の症状は感染した病原体の種類によって異なりますが、一般的には数時間から数日以内に発症し、数日間で回復することが多いです。しかし、腸管出血性大腸菌(O-157など)の感染では、重症化すると溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こし、腎不全や脳症を伴う危険な状態になることがあります。そのため、食中毒の症状が強い場合や、血便が見られる場合は、速やかに医療機関を受診する必要があります。
食中毒の予防
 食中毒の予防には、食材の適切な保存と調理が重要です。肉や魚は十分に加熱し、生ものを扱った手や調理器具はしっかりと洗浄・消毒することが必要です。また、ウイルス性の食中毒(ノロウイルスなど)は、人から人への感染も多いため、手洗いや消毒を徹底することが感染拡大を防ぐ鍵となります。症状が軽度であれば、水分補給をしっかり行いながら安静にすることで自然に回復しますが、重症化した場合には医療機関で適切な治療を受けることが必要です。
食中毒の予防には、食材の適切な保存と調理が重要です。肉や魚は十分に加熱し、生ものを扱った手や調理器具はしっかりと洗浄・消毒することが必要です。また、ウイルス性の食中毒(ノロウイルスなど)は、人から人への感染も多いため、手洗いや消毒を徹底することが感染拡大を防ぐ鍵となります。症状が軽度であれば、水分補給をしっかり行いながら安静にすることで自然に回復しますが、重症化した場合には医療機関で適切な治療を受けることが必要です。
乳糖不耐症(ラクターゼ欠乏症)
乳糖不耐症
 乳糖不耐症は、乳製品に含まれる乳糖(ラクトース)を分解する酵素(ラクターゼ)の活性が低下し、消化不良を起こす疾患です。この病気の人が牛乳やヨーグルトなどを摂取すると、消化されない乳糖が腸内にとどまり、発酵を引き起こしてガスが発生し、腹痛や下痢を引き起こします。特にアジア人は乳糖不耐症の割合が高く、成人の多くがある程度の乳糖不耐性を持っているとされています。
乳糖不耐症は、乳製品に含まれる乳糖(ラクトース)を分解する酵素(ラクターゼ)の活性が低下し、消化不良を起こす疾患です。この病気の人が牛乳やヨーグルトなどを摂取すると、消化されない乳糖が腸内にとどまり、発酵を引き起こしてガスが発生し、腹痛や下痢を引き起こします。特にアジア人は乳糖不耐症の割合が高く、成人の多くがある程度の乳糖不耐性を持っているとされています。
乳糖不耐症の症状
 乳糖不耐症の症状は、乳製品を摂取した後に発生することが特徴です。そのため、特定の食品を摂った後に下痢や腹痛が出る場合には、この病気を疑う必要があります。症状の重さは個人差があり、少量の乳製品なら問題なく摂取できる人もいれば、わずかな乳糖でも強い症状を示す人もいます。
乳糖不耐症の症状は、乳製品を摂取した後に発生することが特徴です。そのため、特定の食品を摂った後に下痢や腹痛が出る場合には、この病気を疑う必要があります。症状の重さは個人差があり、少量の乳製品なら問題なく摂取できる人もいれば、わずかな乳糖でも強い症状を示す人もいます。
乳糖不耐症の対処法
 乳糖不耐症の対処法としては、乳糖を含む食品を避けることが基本ですが、最近では「乳糖分解酵素」を含むサプリメントや、乳糖をあらかじめ分解した「低乳糖ミルク」なども市販されています。チーズやバターなどの発酵食品は、乳糖の含有量が少ないため、症状が軽い人であれば摂取できることもあります。食生活を工夫することで、乳糖不耐症の症状を抑えながら、栄養バランスを維持することが可能です。
乳糖不耐症の対処法としては、乳糖を含む食品を避けることが基本ですが、最近では「乳糖分解酵素」を含むサプリメントや、乳糖をあらかじめ分解した「低乳糖ミルク」なども市販されています。チーズやバターなどの発酵食品は、乳糖の含有量が少ないため、症状が軽い人であれば摂取できることもあります。食生活を工夫することで、乳糖不耐症の症状を抑えながら、栄養バランスを維持することが可能です。
下痢や腹痛が続くとはどういう状態なのか?正常な状態との違い
 下痢や腹痛が続くというのは、単なる一時的な消化不良や食あたりとは異なり、長期間にわたって便の異常や腹部の痛みが続く状態を指します。通常、食べ過ぎや軽いウイルス感染などによる下痢や腹痛は、数日以内に自然に改善します。しかし、1週間以上下痢や腹痛が続く場合、それは消化器系に何らかの異常が生じている可能性が高く、専門的な診察が必要となります。
下痢や腹痛が続くというのは、単なる一時的な消化不良や食あたりとは異なり、長期間にわたって便の異常や腹部の痛みが続く状態を指します。通常、食べ過ぎや軽いウイルス感染などによる下痢や腹痛は、数日以内に自然に改善します。しかし、1週間以上下痢や腹痛が続く場合、それは消化器系に何らかの異常が生じている可能性が高く、専門的な診察が必要となります。
下痢
 下痢の定義としては、通常よりも水分を多く含んだ便が頻繁に出る状態を指します。健康な人でも、食事内容やストレスの影響で一時的に軟便になることはありますが、これが慢性的に続く場合は注意が必要です。例えば、1日に3回以上の水様性の便が続く、便に血が混じる、悪臭が強い、脂っこい便が出るなどの異常が見られる場合は、消化器官に問題が起こっている可能性があります。
下痢の定義としては、通常よりも水分を多く含んだ便が頻繁に出る状態を指します。健康な人でも、食事内容やストレスの影響で一時的に軟便になることはありますが、これが慢性的に続く場合は注意が必要です。例えば、1日に3回以上の水様性の便が続く、便に血が混じる、悪臭が強い、脂っこい便が出るなどの異常が見られる場合は、消化器官に問題が起こっている可能性があります。
腹痛
 また、腹痛が続く場合も要注意です。通常の腹痛であれば、一時的な痙攣や張りが原因であり、数時間から1日以内に自然に軽快することがほとんどです。しかし、下痢とともに激しい腹痛が続く場合や、食後に必ず腹痛が起こる場合は、腸の炎症や腸閉塞、胆嚢や膵臓の病気などが関与している可能性があります。特に、痛みが波のように強弱を繰り返す場合や、じわじわと悪化していく場合は、緊急性が高い疾患が疑われることもあります。
また、腹痛が続く場合も要注意です。通常の腹痛であれば、一時的な痙攣や張りが原因であり、数時間から1日以内に自然に軽快することがほとんどです。しかし、下痢とともに激しい腹痛が続く場合や、食後に必ず腹痛が起こる場合は、腸の炎症や腸閉塞、胆嚢や膵臓の病気などが関与している可能性があります。特に、痛みが波のように強弱を繰り返す場合や、じわじわと悪化していく場合は、緊急性が高い疾患が疑われることもあります。
このように、下痢や腹痛が続くという状態は、単なる一時的な胃腸の不調とは異なり、消化器系に深刻な問題が隠れている可能性があるため、放置せずに医療機関を受診することが大切です。
慢性的な下痢や腹痛の原因として考えられる生活習慣と環境要因
 慢性的な下痢や腹痛の原因は、病気だけでなく、日常の生活習慣や環境要因とも深く関わっています。特に、食事内容やストレス、運動不足、睡眠の質が腸の健康に大きな影響を及ぼします。
慢性的な下痢や腹痛の原因は、病気だけでなく、日常の生活習慣や環境要因とも深く関わっています。特に、食事内容やストレス、運動不足、睡眠の質が腸の健康に大きな影響を及ぼします。
食事
 まず、食生活に関しては、脂肪分の多い食事や加工食品、アルコールやカフェインの過剰摂取が腸に負担をかけることが分かっています。特にファストフードやインスタント食品、刺激の強い香辛料を多く含む食事は、腸の粘膜を刺激し、炎症を引き起こす原因になります。また、乳製品に対する耐性が低い人が牛乳やチーズを過剰に摂取すると、乳糖不耐症によって下痢や腹痛が引き起こされることもあります。
まず、食生活に関しては、脂肪分の多い食事や加工食品、アルコールやカフェインの過剰摂取が腸に負担をかけることが分かっています。特にファストフードやインスタント食品、刺激の強い香辛料を多く含む食事は、腸の粘膜を刺激し、炎症を引き起こす原因になります。また、乳製品に対する耐性が低い人が牛乳やチーズを過剰に摂取すると、乳糖不耐症によって下痢や腹痛が引き起こされることもあります。
ストレス
 ストレスも腸の働きに大きな影響を与えます。腸は「第二の脳」とも呼ばれ、自律神経によってコントロールされています。強いストレスを感じると、交感神経が優位になり、腸の蠕動運動が異常を起こすことがあります。これにより、過敏性腸症候群(IBS)のような機能性腸疾患が発症しやすくなり、慢性的な下痢や腹痛の原因となります。また、仕事や家庭のストレスが原因で不規則な食生活が続くと、腸内環境が乱れ、腸内の悪玉菌が増加して下痢が悪化することもあります。
ストレスも腸の働きに大きな影響を与えます。腸は「第二の脳」とも呼ばれ、自律神経によってコントロールされています。強いストレスを感じると、交感神経が優位になり、腸の蠕動運動が異常を起こすことがあります。これにより、過敏性腸症候群(IBS)のような機能性腸疾患が発症しやすくなり、慢性的な下痢や腹痛の原因となります。また、仕事や家庭のストレスが原因で不規則な食生活が続くと、腸内環境が乱れ、腸内の悪玉菌が増加して下痢が悪化することもあります。
運動不足
 運動不足も腸の機能低下を招く要因の一つです。適度な運動は腸の蠕動運動を促進し、排便をスムーズにしますが、デスクワークが多く運動量が少ない人は腸の働きが鈍くなり、便秘や下痢を引き起こしやすくなります。さらに、睡眠不足や不規則な生活習慣も腸のバランスを崩す原因となります。
運動不足も腸の機能低下を招く要因の一つです。適度な運動は腸の蠕動運動を促進し、排便をスムーズにしますが、デスクワークが多く運動量が少ない人は腸の働きが鈍くなり、便秘や下痢を引き起こしやすくなります。さらに、睡眠不足や不規則な生活習慣も腸のバランスを崩す原因となります。
このように、慢性的な下痢や腹痛には生活習慣が深く関わっており、症状を改善するためには、食事の見直し、ストレス管理、適度な運動、規則正しい生活を心がけることが大切です。
病院を受診するべきタイミングと適切な診断方法
 下痢や腹痛が続く場合、どのタイミングで病院を受診すべきか迷うことがあるかもしれません。一般的に、一時的な下痢や軽度の腹痛は自然に治ることが多いですが、次のような症状が見られる場合は、早急に医療機関を受診することが必要です。
下痢や腹痛が続く場合、どのタイミングで病院を受診すべきか迷うことがあるかもしれません。一般的に、一時的な下痢や軽度の腹痛は自然に治ることが多いですが、次のような症状が見られる場合は、早急に医療機関を受診することが必要です。
受診のタイミング
 ・1週間以上下痢や腹痛が続く
・1週間以上下痢や腹痛が続く
・血便が出る、または黒色便(消化管出血の可能性)
・発熱(38℃以上)が続く
・急激な体重減少がある
・夜間に痛みで目が覚めるほどの強い腹痛
・食事をとるとすぐに下痢をする(吸収不良の可能性)
・便が白っぽい(胆管や肝臓の異常の可能性)
病気の診断
 診断には、まず問診と視診が行われます。医師は症状の経過や食生活、ストレス状況などを詳しく確認し、必要に応じて便検査や血液検査を実施します。便検査では、細菌やウイルス、寄生虫の有無を確認することができます。ウィルス検査は対応している医療機関が限られているため、検査希望の場合にはあらかじめ医療機関へ確認して頂くことをお勧め致します。血液検査では、貧血や炎症の有無、栄養状態、肝機能や膵臓の異常を調べることができます。
診断には、まず問診と視診が行われます。医師は症状の経過や食生活、ストレス状況などを詳しく確認し、必要に応じて便検査や血液検査を実施します。便検査では、細菌やウイルス、寄生虫の有無を確認することができます。ウィルス検査は対応している医療機関が限られているため、検査希望の場合にはあらかじめ医療機関へ確認して頂くことをお勧め致します。血液検査では、貧血や炎症の有無、栄養状態、肝機能や膵臓の異常を調べることができます。
病気の検査
 また、潰瘍性大腸炎やクローン病、大腸がんなどが疑われる場合には、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)が必要になることがあります。この検査では、腸内の粘膜の状態を直接観察し、必要に応じて組織を採取して病理検査を行うことができます。さらに、CTやMRIなどの画像検査を併用することで、腸の炎症や腫瘍の有無を詳しく調べることができます。
また、潰瘍性大腸炎やクローン病、大腸がんなどが疑われる場合には、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)が必要になることがあります。この検査では、腸内の粘膜の状態を直接観察し、必要に応じて組織を採取して病理検査を行うことができます。さらに、CTやMRIなどの画像検査を併用することで、腸の炎症や腫瘍の有無を詳しく調べることができます。
症状が軽いからといって放置すると、病気が進行してしまうこともあります。少しでも異常を感じたら、早めに医師の診察を受けることが重要です。
ご予約はこちらから
当院では、下痢や腹痛でお悩みの方に丁寧に診察と検査を行います。場合によっては、内視鏡検査のご提案もいたします。大腸カメラを希望される場合にはWebにて大腸カメラを直接ご予約頂くことも可能となっております。外来、内視鏡検査はいずれも24時間web予約が可能です。